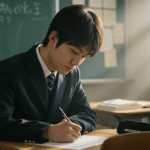「どうしてあの時、指定校推薦を取らなかったんだろう…。」
大学受験を経験した人の中には、そんな後悔の気持ちを抱え続けている人が少なくありません。
推薦で早々に合格を決めた友人を横目に、模試や共通テストに追われる日々。結果が伸び悩むと、心の中に必ず浮かぶのは「もし指定校推薦を選んでいたら、もっと楽に合格できたのでは?」という“もしも”の思い。
実は、この後悔はあなただけのものではありません。多くの受験生が同じ気持ちを経験し、そしてそこから自分なりの答えを見つけています。
この記事では、「指定校推薦を取ればよかった」と感じる瞬間や理由を深掘りしつつ、後悔を前向きな力に変えるための考え方と具体的な行動を徹底解説します。続きを読めば、「あの選択にも意味があった」と思えるヒントが必ず見つかります。
なぜ「指定校推薦 取ればよかった」と思うのか?
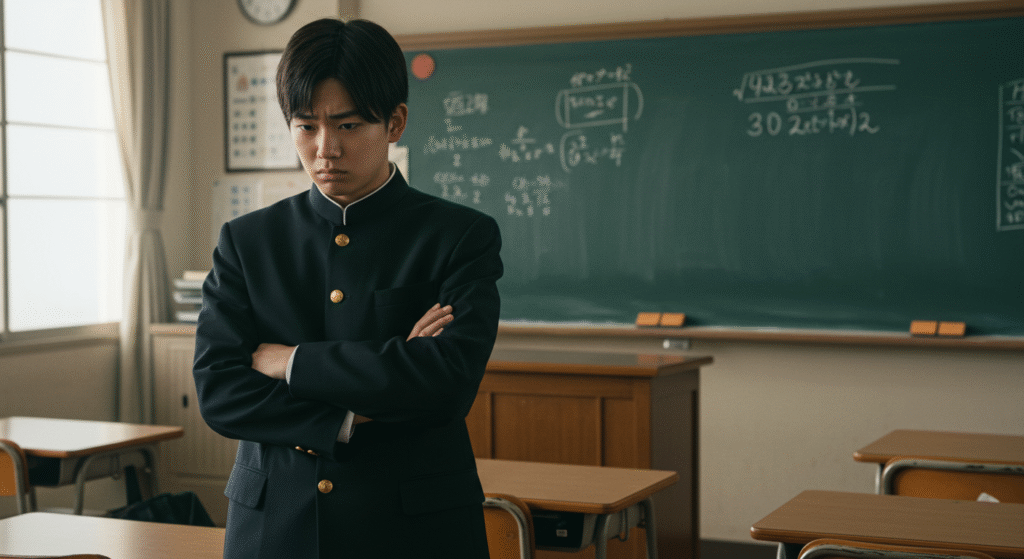
「指定校推薦を取ればよかった」と感じる背景には、単なる後悔ではなく、受験を乗り越える過程で積み重なった不安や焦りが関係しています。
ここでは、多くの人がどのような場面でその気持ちを抱くのかを整理し、どんな心理が働いているのかを深く見ていきます。
合格の安心感を得られなかった後悔
指定校推薦は、早い段階で合格が決まる点が大きな特徴です。
そのため一般受験に進んだ場合、秋から冬にかけて精神的な負担が大きくなりやすく、
- 「もしあの時、指定校推薦を選んでいたら…」
- 「こんなに不安な時期を過ごさずに済んだかもしれない」
と考えてしまうことがあります。
一般受験のストレスは大きい
文部科学省も、受験期は精神的負荷が高まりやすいと指摘しています。
参考:https://www.mext.go.jp/
プレッシャーが強くなるほど、確実な進路が決まる選択肢に魅力を感じやすくなる傾向があります。
その結果、「なぜあのとき指定校推薦を選ばなかったのか」と自分を責めてしまうきっかけになることがあります。
周りの状況がより強い焦りを生む
推薦で進路が決まった同級生が増えていくと、安心している姿が目に入る機会も増えます。
自分だけが受験の不安を抱えているように感じ、指定校推薦を選ばなかったことが急に重くのしかかるように見えてきます。
周囲が早く進路を決める中での焦りと比較
指定校推薦を選んだ人は、早ければ秋には進路が決まります。
一方、一般受験組はそこからが本番で、気持ちの余裕も時間も少なくなっていきます。
友達が進路を確定し始める時期の心理
周囲が受験から解放されていく姿を見ると
- 「自分だけ取り残されている気がする」
- 「あっちの選択肢を選んでいれば、もっと気持ちが楽だったのかな」
と感じることがあります。
これは、人がもともと持つ比較の習性によるものです。
人間は「周りより不利な状況」に置かれていると感じたとき、焦りが一気に高まります。
その結果、選ばなかった選択を高く評価してしまう心理が働きます。
冬の時期に後悔が強まりやすい理由
検索データを見ると、
「指定校推薦 取ればよかった」という言葉が増えるのは 12〜2月 です。
この時期は
- 推薦組は完全に進路確定
- 一般組は本番直前で不安のピーク
- 合否が出始める時期でもある
と、心理的な負荷が最大になるタイミング。
そのため、指定校推薦を選ばなかったことがより強く頭に浮かびやすくなります。
一般受験で苦戦したときの“もしも”の気持ち
一般受験は最後まで結果が読めません。
そのため、うまく進まなかったときには「もし指定校推薦を取っていたら」という考えが浮かぶことがあります。
成績が伸び悩むときに起こる心の揺れ
模試の結果が安定しない、志望校判定が思うように上がらないなど、壁を感じる場面は誰にでもあります。
そんなときほど、「安定した進路を持っている人」が羨ましく見えやすいものです。
不合格が続くと自分を責めやすくなる
受験は努力しても結果が伴わないことがあります。
うまくいかない時期が続くと、
- 「なぜあのとき挑戦しなかったのか」
- 「指定校を持っていれば、ここまで落ち込まずに済んだかも」
という“もしも”が増えていきます。
不合格の経験はつらいものですが、それと「指定校推薦を取るべきだったかどうか」は別の話です。
過去の選択を否定してしまうほど、受験の精神的負荷は大きいということでもあります。
選んだ道にも別の悩みが存在する
実は、指定校推薦で進んだ人でも、
- 「自分はもっと挑戦できたのでは…」
- 「推薦だから入学後が不安」
と別の悩みを抱えることがあります。
どの選択をしても、その瞬間の状況によって“別の道が良く見える”ことはあります。
後から浮かぶ感情は、「あのときの自分の精一杯の判断を、今の目線で見つめ直しているだけ」と言えます。
指定校推薦を取らなかった人が後悔する瞬間
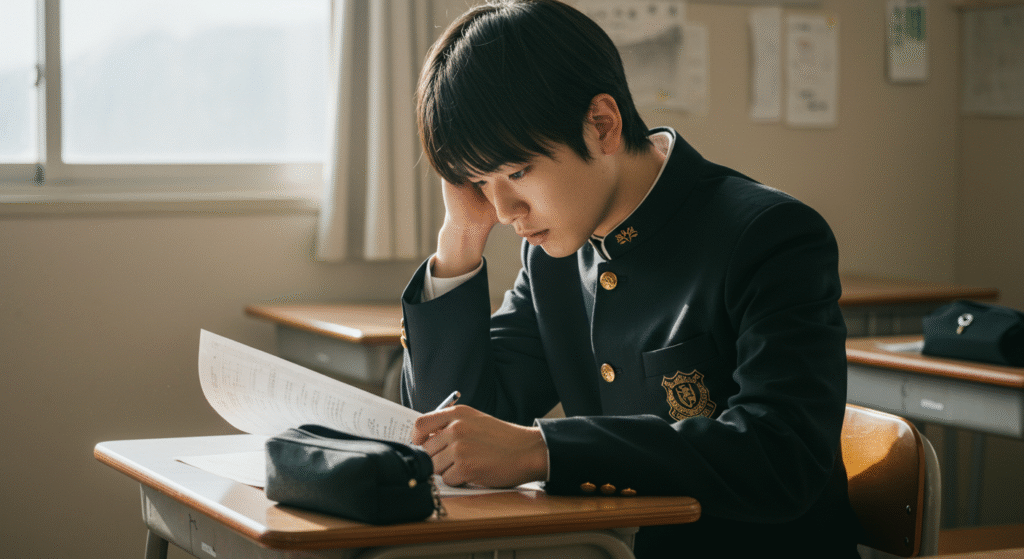
指定校推薦を選ばなかった、または校内選考で通らなかった人の多くは、受験期間のどこかで「取ればよかった」と感じる場面に出会います。
その気持ちは、結果だけでなく“その時に抱えた不安や焦り”も深く関係しています。
ここでは、特に後悔が大きくなりやすい瞬間をわかりやすくまとめました。
9月の校内選考で候補から外れたとき
指定校推薦は、まず学校内で誰が推薦枠に入るかが決まります。
9月頃に行われる校内選考は、受験生にとって最初の大きな分岐点です。
校内選考の結果を見た瞬間に感じる後悔
候補から外れたとき、多くの人が次のような気持ちを抱きます。
- 「もっと評定を上げておけばよかった」
- 「夏休みに提出書類をしっかり準備すればよかった」
- 「挑戦しなかった自分に後悔が残る」
指定校推薦は評定平均だけでなく、日頃の態度や提出物なども判断材料として使われる学校が多いです。
(参考:文部科学省「進路指導資料」https://www.mext.go.jp/)
ただ、校内選考に漏れた瞬間は、自分の努力が否定されたように感じやすく、
「取っておけばよかった」という気持ちが強くなりがちです。
まわりが推薦準備に進む姿を見るつらさ
周囲が志望理由書の作成や面接練習に進むと、自分だけがスタートラインに立てていないように感じることがあります。
「もっと早く動いておけばよかった」と思う瞬間が増え、心が揺れやすくなります。
12月、推薦合格者の喜びを見たとき
12月になると、指定校推薦や総合型選抜の合格発表が一気に増えます。
学校の雰囲気も大きく変わり、進路が決まった生徒の喜びが目立つ時期です。
合格報告が続くと気持ちが揺れやすくなる
推薦組は、
- 安心した顔で学校生活を送っている
- 年末をリラックスして過ごしている
- 受験勉強から解放されている
という状態になります。
その姿を見ると、一般受験を選んだ人は自然と自分と比較してしまい、
- 「私もあんな気持ちになれたはずなのに」
- 「なぜ指定校推薦を受けなかったのか」
と、選択を後悔しやすくなります。
冬休みの空気感の差が大きく感じられる
12月〜1月は共通テスト直前で精神的に最も揺れやすい時期です。
そんな中、推薦組が落ち着いた雰囲気でいるのを見ると、
不安に押されて“もしあの時…”という気持ちが強くなります。
共通テスト・二次試験で伸び悩んだとき
共通テストや二次試験が近づくほど、勉強量が増える一方で、思うように結果が出ないことがあります。
この時期に「取ればよかった」と感じる人はとても多いです。
点数が安定しないと、選ばなかった道がよく見える
- 模試の判定が下がる
- 過去問の点数が伸びない
- 得意科目で失敗する
など、思いどおりにいかない場面が増えます。
すると、
- 「指定校推薦ならもう進路が決まっていたのに」
- 「ずっとこんなに苦しい思いをしなくて済んだのでは」
という考えが浮かびやすくなります。
不安が強いと“確実な道”が魅力的に見える
文部科学省が公表している生徒指導資料でも、受験期はストレスが大きく、判断が後ろ向きになりやすいと示されています。
(参考:https://www.mext.go.jp/)
不安が増えるほど、
選ばなかった“確実に見える選択肢”の価値を高く感じるのは自然な反応です。
最終的に志望校に届かなかったとき
最後に合格発表を迎えた瞬間、後悔が最も大きくなる人はたくさんいます。
合格発表は気持ちが一気に揺れやすい
志望校に届かなかった場合、
「指定校推薦を選んでいれば進路は決まっていたかもしれない」
という考えが自然に浮かびます。
これは、結果を受け止める前にどうしても起こりやすい気持ちです。
自分の歩んだ道を否定したくなる瞬間
努力した道が結果に結びつかなかった時、
過去の選択を振り返ってしまうのはごく普通のことです。
- 「あのときの選択が正しかったのか」
- 「別の道を選んでいればもっと楽だったのでは」
と思うのは、長い受験生活がおわり、心が疲れている証拠でもあります。
その後に気づくこともある
指定校推薦を選ばなかった人の中には、
あとから「この道で良かった」と感じる場面が出てくることもあります。
- 最後まで努力した経験が自信になる
- 違う大学に進んだけれど満足している
- あのとき悩んだことが、その後の進路選択に役立った
受験で味わった悔しさや不安も、必ずしも無駄にはなりません。
後悔しないために知っておくべき考え方
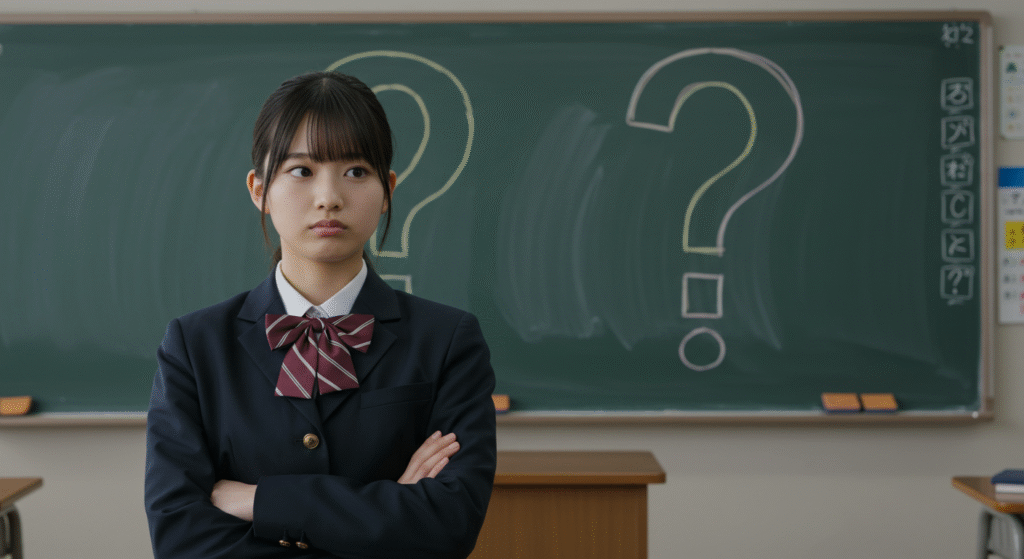
「指定校推薦を取ればよかった」と感じるとき、多くの人は“今の不安”“過去の選択への迷い”“周りとの比較”が重なっています。
受験は人生の中でもプレッシャーの大きい時期だからこそ、選ばなかった道がよく見えてしまうものです。
ここでは、その後悔を少しでも軽くし、今の自分の選択に意味を見出しやすくなる視点を整理しました。
「推薦=逃げ」ではない!正しい選択基準とは
指定校推薦は「逃げ」や「ラクな選択」と思われがちですが、制度の本質はまったく違います。
推薦は“長期間の取り組み”が評価される制度
文部科学省の資料では、推薦入試は高校での学習状況や日頃の取り組みを踏まえて選抜する方式と説明されています。
参考:https://www.mext.go.jp/
授業態度、提出物、定期テスト、学校生活の積み重ねが形になる仕組みです。
これらは短期間で作れるものではなく、むしろ「コツコツ頑張ってきた人が評価される道」といえます。
また、推薦枠を得るためには評定平均を維持し続ける必要があります。
安定した成績管理は簡単なことではなく、地道な努力が求められます。
“自分のタイプに合うかどうか”で決めるほうが後悔しにくい
推薦か一般受験かを判断する際に大切なのは、「どちらが正しいか」ではなく、
“どちらが自分に向いているか” という視点です。
- 長期戦に向いているタイプか
- 評定維持が得意か
- 面接が苦手か得意か
- 精神的にどちらが負担が少ないか
- 行きたい大学に推薦枠があるか
こうした要素で判断するほうが、後からの後悔は少なくなります。
推薦を取らなかった場合の成功例と学び
推薦を選ばず一般受験に挑んだ人の中にも、結果的に「この道で良かった」と感じる人がいます。
その背景には、努力のプロセスを通して得た成長があります。
一般受験の経験が“自分の力”になることも多い
推薦を使わなかったことで、
- 志望校の選択肢が広がった
- 勉強にしっかり向き合えた
- 受験を乗り越えた経験が自信につながった
という実感を持つ人はたくさんいます。
受験勉強の習慣は大学生活にも良い影響を与えます。
「自分で計画し努力を続ける経験」は、その後の進路選択にも生きていきます。
あとから“あれでよかった”と納得できる瞬間もある
大学に進学してから、
- 「この大学に来てよかった」
- 「受験で苦労したからこそ今がある」
と感じる人も多いです。
受験直後は気づけなくても、時間が経つにつれ、一般受験を選んだ意味がはっきりしてくることがあります。
指定校推薦を選んだ人が感じる意外な悩み
「指定校推薦を取ればよかった」と思う側とは反対に、
指定校推薦を選んだ人にも、別の悩みが生まれることがあります。
推薦で合格したからこそ生まれる不安やプレッシャー
推薦で進学した人の中には、
- 「入学後についていけるか不安」
- 「一般受験だったら受からなかったかもしれない」
- 「推薦だからと言われたくない」
という気持ちを抱くことがあります。
推薦組は“安心して進路が決まる”というメリットがある一方、
その安心感と引き換えに別のプレッシャーが生まれる場合もあります。
どちらを選んでも“迷い”は生じる
人は、選ばなかった道のほうを良く見てしまう傾向があります。
これは受験期のストレスが強いほど起こりやすい現象です。
つまり、一般受験を選んだ人が「推薦にすればよかった」と思うように、
推薦を選んだ人も「一般で挑戦すべきだったかも」と悩むことがあります。
どちらを選んでも、必ず何かしらの迷いが生まれるものだと知っておくと、
今抱えている気持ちが少し軽くなるはずです。
今からでもできる“気持ちの切り替え方”
後悔の気持ちは自然に湧くものですが、そのまま引きずる必要はありません。
ここからの行動次第で、受験直後の気持ちは大きく変わります。
① 推薦を取らなかった理由を整理してみる
「どうして推薦を選ばなかったのか」を具体的に書き出してみると、
その時の判断が決して間違いではなかったと気づけることがあります。
- 評定が届かなかった
- 面接より筆記試験の方が得意だった
- 志望校に推薦枠がなかった
- 一般受験で挑戦したかった
その理由を改めて見つめることで、自分の選択を肯定しやすくなります。
② “今できる行動”に意識を向ける
受験期であれば、
- 共通テストの見直し
- 二次試験対策の強化
- 出願校の調整
など、まだできることが残っています。
大学進学後であれば、
- 興味のある授業を積極的に取る
- 新しい活動に挑戦する
- 資格取得に向けて勉強する
と、進路を切り開く選択肢はいくらでもあります。
③ 過去より“これからの選択”を重視する
受験はひとつの通過点にすぎません。
大学で何を学び、どんな経験を積むかで将来は大きく変わっていきます。
後悔を抱えている今の気持ちも、
これからの選択を良いものにするヒント と考えると、前に進みやすくなります。
指定校推薦を検討している人へのアドバイス

「指定校推薦を取ればよかった」と後悔する人が多い一方で、
実際に迷っている段階では何を基準に決めればいいのか分からない人もたくさんいます。
推薦は早く進路が決まるという大きなメリットがありますが、その一方で「本当にこの選択でいいのか」という不安もつきまといます。
ここでは、迷っている人が判断しやすくなるように、考えるべき視点や準備のポイントを整理しました。
取るか迷ったら整理すべき3つの視点(学力・将来像・学校枠)
指定校推薦に挑戦するかどうかは、「受かるかどうか」だけで決めると後悔しやすくなります。
大切なのは、自分が納得できる基準 を持つことです。
【学力】評定と一般受験の伸びしろを冷静に比べる
まず確認したいのが、自分の現在の学力です。
- 評定平均が推薦基準を満たしているか
- 今から一般受験で成績を伸ばせる見込みがあるか
- 得意科目と苦手科目の差はどれくらいか
文部科学省の資料でも、推薦入試は学校の学習状況を重視する制度と明記されています。
参考:https://www.mext.go.jp/
評定が安定している人にとって指定校推薦は現実的な選択になりやすい一方、
「一般ならもっと上が目指せる」と感じる場合は慎重に検討する必要があります。
【将来像】大学で何を学びたいのかを言葉にしてみる
推薦を選ぶかどうかを決める際は、
「入りたい大学」よりも「そこで何を学びたいか」 を考えることが重要です。
- 学びたい分野がその大学にあるか
- 卒業後の進路をどう描いているか
- その大学で得たい経験は何か
推薦枠があるからという理由だけで決めると、後から「もっと別の大学を見ればよかった」と感じる可能性があります。
【学校枠】どんな大学の推薦枠があり、自分に合うかを確認する
指定校推薦は学校ごとに枠が違うため、
その年にどんな大学が来ているか を把握しておくことも重要です。
- 希望する大学の枠があるか
- 同じ学科でも複数の大学が選べるか
- 競争率が高そうかどうか
校内選考の仕組みは学校によって異なります。
先生に「どういう基準で毎年選んでいるのか」を確認しておくと判断しやすくなります。
家族や先生と話し合うときのチェックポイント
推薦か一般かで迷っているときは、ひとりで抱え込まず、家族や先生と相談することも大切です。
ただ話すだけではなく、「何を話すべきか」を明確にしておくと有意義になります。
① 現実的な可能性を聞く
先生に相談するときは、次のような点を確認しておくと判断材料になります。
- 校内選考で通る見込みはあるか
- 過去の合格者の評定や様子
- 推薦後の学習の進み方や注意点
自分の状況を客観的に見てもらうことで、選択が現実的かどうかが分かりやすくなります。
② 家族とは経済面・大学生活について話す
大学進学は学費や生活費も関わる選択です。
- 一般受験で浪人した場合の費用
- 推薦で早く進路が決まるメリット
- 一人暮らしになる場合の負担
こうした点を確認しておくと、「どちらの選択でも納得しやすい状態」が作れます。
③ 自分の希望を言語化し、相手に伝える
「なんとなく推薦」「なんとなく一般」ではなく、
自分がどうしたいかを言葉にして伝えることが大切です。
- どんな大学生活を送りたいのか
- なぜ推薦(または一般)に気持ちが傾いているのか
- 不安に感じていることは何か
これらを整理しておくと、周囲も適切なアドバイスをしやすくなります。
推薦を取るなら入学後の学び続ける姿勢が必須
指定校推薦は大学への“入学ルート”であって、“ゴール”ではありません。
推薦で合格すると、どうしても「安心して気が抜けてしまう」という声もあります。
しかし、それが後々の後悔につながることもあります。
入学後にギャップを感じないために知っておくこと
推薦で進学した人が抱きやすい悩みには、
- 授業についていけるか不安
- 一般受験組との差を感じる
- 「推薦だから」と言われないか心配
というものがあります。
これは珍しいことではなく、“推薦特有の心理”とも言えます。
入学後の姿勢次第でプラスにもマイナスにもなる
推薦で入学した学生でも、入学後の努力次第で強みを伸ばすことができます。
- 興味のある授業を積極的に履修する
- 資格取得を目指す
- サークルやプロジェクトに参加し経験を積む
こうした行動を積み重ねていけば、推薦で入ったことが気にならなくなるどころか、
「早く進路が決まった分、時間を有効に使えた」と感じられるようになります。
推薦は“楽な道”ではなく“準備を早く始められる道”
推薦で進んだ人は、一般受験よりも早く大学生としての準備を始められます。
- 合格発表後に教養書を読んでみる
- 大学のシラバスを確認しておく
- 将来の目標を改めて考える
こうした前向きな準備を始めることで、推薦入学のメリットが大きくなります。
後悔をプラスに変える具体的アクション
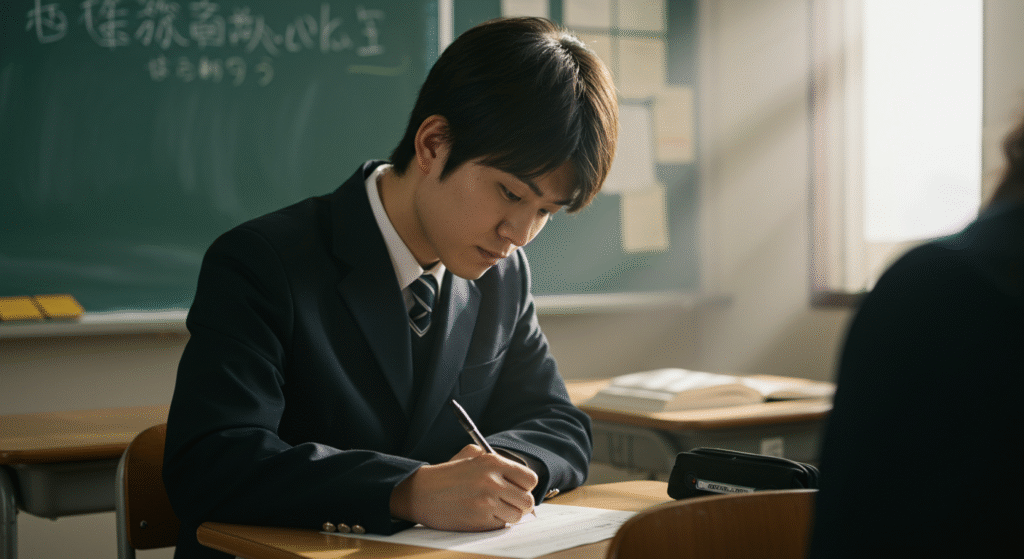
「指定校推薦を取ればよかった」という後悔は、決して“弱さ”ではなく、
それだけ受験や進路に本気で向き合ってきた証です。
ただ、後悔のまま立ち止まってしまうと、自分の可能性を狭めてしまうこともあります。
ここでは、その気持ちを前向きな行動に変えていくための具体的なステップを整理しました。
これからどう動けばいいかが明確になると、「自分の選んだ道にも意味があった」と感じやすくなります。
推薦を逃した後の再挑戦戦略(一般受験・浪人・他の推薦)
指定校推薦に挑戦できなかった、あるいは校内選考で落ちてしまったとしても、
進路の選択肢がなくなるわけではありません。
一般受験で逆転を狙う場合
一般受験は、努力が直接結果に結びつく可能性が高い選抜方式です。
ここから逆転を狙うために意識したいのは次の3つです。
- 出願戦略を見直す:安全校〜挑戦校までバランスを取る
- 弱点科目の集中対策:過去問から失点パターンを割り出す
- 勉強時間より“質”を重視する:短時間でも内容濃く取り組む
一般受験の魅力は、最後まで可能性が開かれている点です。
推薦で悔しい思いをした人ほど、強い集中力を発揮できることもあります。
浪人という選択肢を現実的に考える
浪人は簡単な決断ではありませんが、
「今の学力と志望校の差が大きい」「どうしても行きたい大学がある」
という場合には有効な選択肢です。
浪人を選ぶ場合に確認しておきたいポイントは以下です。
- 一年間の学費・生活費の負担
- 家族の理解が得られるか
- 予備校や通信教材など学び方の選択
- 自分が本当に一年間走り切れるか
浪人は覚悟が必要ですが、自分の軸を持って挑戦できる人にとっては大きなチャンスにもなります。
他の推薦(総合型・公募推薦)を検討する
指定校推薦を逃したとしても、推薦入試には他にも種類があります。
- 総合型選抜(旧AO入試):意欲・適性・ポートフォリオが評価される
- 公募制推薦:小論文、面接、基礎学力テストなど複数の形式がある
文部科学省の資料にも、推薦入試は多様な評価軸があると記されています。
参考:https://www.mext.go.jp/
指定校推薦にこだわりすぎず、別の推薦方式で可能性を広げるのも現実的な判断です。
ただし、総合型選抜や公募制推薦は、
「何を評価されるのか」「どんな準備が必要か」が分かりづらく、
独学だと対策が後手に回りやすいのが難点です。
そこで、
総合型選抜・推薦入試に特化した対策ができる
【オンラインのメガスタ】 を活用する受験生が増えています。
- 志望理由書や小論文の作成をゼロからサポート
- 面接対策も1対1または少人数制でじっくり指導
- 各大学の採点基準に基づいた「評価される書き方・話し方」を習得できる
- オンライン完結で通塾時間ゼロ
- 他塾より料金が安く、継続しやすい
指定校推薦を逃したとしても、
他の推薦方式で逆転を狙うことは十分に可能です。
そのためには、大学側が何を重視しているのか理解し、的確な準備を進めることが重要になります。
オンラインのメガスタの詳細はこちら
https://www.online-mega.com/?utm_source=a8&utm_medium=affiliate
後悔から学ぶ「自分に合った進路選び」
後悔は、次の行動をより良いものにするヒントにもなります。
「なぜ後悔したのか」を丁寧に振り返ることで、自分に合った進路選びが見えてきます。
自分の“判断基準”を知るきっかけになる
指定校推薦を取らなかった理由や、その時に抱えていた不安を振り返ると、
- 安定した選択をしたかったのか
- 自分で限界まで挑戦したかったのか
- 評定を維持するのが難しかったのか
など、自分がどういう考え方をするタイプなのかが見えてきます。
進路選びは「偏差値」だけで決めるものではなく、
自分の性格や、どんな環境で輝けるか を知ることで精度が上がります。
将来像を再確認するチャンスにもなる
後悔する気持ちは、「本当はこうしたかった」という心の本音を示してくれることもあります。
- もっと挑戦した進路に行きたかった
- 自分の好きな分野を深く学びたい
- 入ったら満足しない大学に進みたくなかった
こうした気持ちは、進路を再構築するヒントになります。
“選ばなかった道の魅力”に引っ張られていないか確認
受験期は不安が大きく、“逃した選択肢”が実際より良く見える傾向があります。
その心理を理解しておくと、冷静に進路を考えられるようになります。
指定校推薦を取らなかった経験が活きる場面
指定校推薦を取らなかったことは、必ずしもデメリットだけではありません。
むしろ、経験としてプラスに働く場面もあります。
諦めずに努力する力が身につく
一般受験に挑んだ人の多くは、
- 計画性
- 自己管理能力
- 粘り強さ
といった“社会に出ても役立つ力”を身につけています。
これらは受験勉強を続けた時間があってこそ得られるものです。
進路を深く考えるきっかけになる
指定校推薦を選ばなかったことで、
- 自分はどんなことに熱中できるのか
- どういう環境で力を発揮できるのか
- 何を目指して大学に行くのか
を改めて考え直す時間が生まれます。
これは、大学入学後の学びにも良い影響を与えます。
自分の選択に責任を持てるようになる
推薦を取らなかった経験は、
「自分の選択に向き合う力」を育ててくれます。
- 選ばなかった理由を説明できる
- 結果を受け止めて前に進める
- 失敗してもやり直す方法を考えられる
こうした力は、大学生活や社会に出てからも役立つ重要なスキルです。
まとめ
「指定校推薦を取ればよかった」と感じる人は多いですが、その後悔をどう受け止め、どう行動につなげるかが未来を大きく左右します。
ここで解説した重要なポイントを、分かりやすく整理します。