共通テストが終わった瞬間、「やばい、全然できなかった…」と頭が真っ白になった人はいませんか? 模試では手応えがあったのに、本番では点が伸びない。だけど不思議と、記述中心の二次試験では得点できる感覚がある。
もしあなたが今そんな状況にいるなら、まだ逆転のチャンスは残されています。この記事では、共通テストで失敗しても二次試験で勝ち切るための戦略と実例を徹底解説します。
共通テストはできないけど二次試験はできる―その状況の背景

「共通テストが思ったより取れなかった」
「模試では書けていたのに、本番では点にならなかった」
それでも、「二次試験なら戦える気がする」と感じている人は少なくありません。
「共通テストできない 二次できる」と検索している背景には、単なる不安だけでなく、自分の得意・不得意をうっすら理解している感覚があります。
ここではまず、「なぜこの状況が起こるのか」を整理しながら、あなたの感覚が間違っていない可能性を言語化していきます。
なぜ共通テストで点が伸びないのか(形式・スピード・処理能力の壁)
共通テストで点が伸びにくい理由は、学力不足だけとは限りません。
試験の形式そのものが合わないケースも多くあります。
マーク式特有の処理スピードが合わない
共通テストは、限られた時間の中で大量の情報を処理し続ける試験です。
文章量が多く、設問の意図を素早くつかめないと、実力があっても点に結びつきません。
- 読解に時間がかかる
- 見直しの余裕がない
- 後半で集中力が切れてしまう
こうした傾向がある人は、共通テストでは不利になりやすいです。
「正解を選ぶ」ことへの苦手意識
マーク式では、「どれが一番正しいか」を選び切る力が求められます。
途中まで考えられていても、最後の選択で迷い、失点することもあります。
これは思考力がないのではなく、処理の形式が合っていない可能性があります。
二次試験で得点できる人の特徴(記述力・思考力・論理展開力)
一方で、二次試験になると急に手応えを感じる人がいます。
そこには、いくつか共通する特徴があります。
考えた過程を言葉で表現できる
二次試験では、途中式や考え方、理由づけが評価されます。
多少計算ミスや表現の甘さがあっても、考え方が伝われば点が入ることがあります。
- 答えに至る流れを書ける
- 自分の言葉で説明できる
- 条件を整理して論理的につなげられる
こうした力は、マーク式より記述式で発揮されやすいです。
「時間をかけて考える」試験との相性
二次試験は、問題数が絞られている分、1問に向き合う時間があります。
じっくり考えるタイプの受験生にとっては、力を出しやすい形式です。
共通テストで感じた焦りが、二次試験では落ち着きに変わる人もいます。
読者がこの記事にたどり着く本当の理由
(「失敗を取り戻したい」「逆転合格の可能性を知りたい」)
このキーワードで検索している人は、
「楽観的な言葉」を探しているわけではありません。
本当は、もう一度現実を整理したい
- 共通テストの結果を見て落ち込んだ
- でも、完全に諦めきれない
- 二次試験に向けて動く価値があるのか知りたい
こうした気持ちが重なって、このページにたどり着いています。
「自分だけじゃない」と確認したい気持ち
共通テストがうまくいかなかったとき、
「周りはできているのに、自分だけ失敗した」と感じがちです。
だからこそ、
同じような状況から立て直した人がいるのか
この感覚は間違っていないのか
それを確かめたくなります。
この記事では、その不安をごまかさず、
「なぜそう感じるのか」「どこに可能性が残っているのか」を丁寧に整理しています。
共通テストがすべてではありません。
あなたが感じている「二次ならできるかもしれない」という感覚には、理由があります。
よくある解説内容とその限界
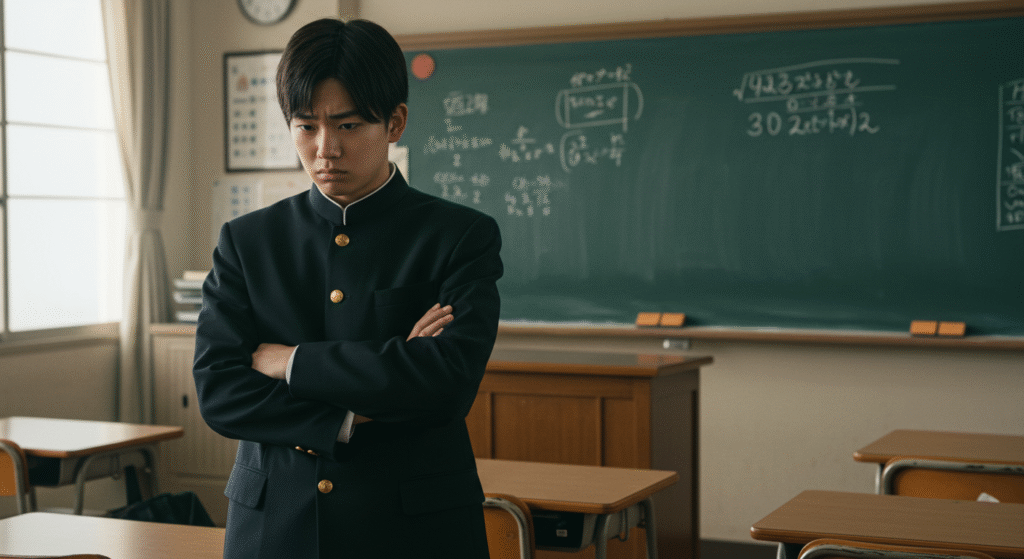
「共通テストができなかったけど、二次試験で挽回できるか知りたい」
そう思って検索してみると、ある程度似た内容の解説にたどり着く人が多いはずです。
もちろん、それらの解説が間違っているわけではありません。
ただし、今まさに共通テストでつまずいた受験生の不安に、十分に応えきれていない部分もあります。
ここでは、よく見かける解説内容を一度整理しながら、
「なぜそれだけでは不安が消えないのか」「どこが足りないのか」を丁寧に見ていきます。
形式に慣れる・時間配分を改善するという一般論
「共通テストは形式に慣れれば点が伸びる」
「時間配分を意識すれば解けるようになる」
こうした説明は、ほとんどの解説記事で触れられています。
たしかに、共通テストは情報量が多く、処理スピードが求められる試験です。
形式への慣れや時間配分の工夫が必要なのは事実でしょう。
ただ、共通テストを終えた“今”の受験生にとって、
この説明はどこか空回りしやすい側面があります。
- もう本番は終わっている
- 今から形式に慣れても点数は変わらない
- 「できなかった理由」は分かっている
こうした状態の人にとって、
「慣れれば伸びる」という言葉は、慰めにも対策にもなりにくいのが現実です。
本当に知りたいのは、
「慣れなかった結果、これからどう判断すればいいのか」
その部分ではないでしょうか。
模試活用や過去問練習といった定番アドバイス
次によく出てくるのが、模試や過去問の活用です。
ポイント
- 模試で立ち位置を確認する
- 過去問を繰り返して傾向をつかむ
- 点数の推移を見て判断する
これらも、受験勉強全体としては大切な考え方です。
しかし、「共通テストできない 二次できる」と検索している人の多くは、
すでに模試も過去問も、それなりにやってきたはずです。
それでも、
- 模試では書けていたのに、本番では取れなかった
- 過去問では通用していたのに、共通テストでは点にならなかった
こうしたズレに直面しています。
その状態で「もっと模試を活用しよう」「過去問をやり込もう」と言われても、
具体的に何をどう変えればいいのかが見えにくいのです。
単なる量や回数の話ではなく、
「今の自分の結果をどう解釈するか」という視点がないと、不安は残ったままになります。
不足しがちな“戦略的な出願視点”
多くの解説で意外と触れられていないのが、出願全体をどう見るかという視点です。
共通テストの結果が出たあと、受験生が本当に悩んでいるのは、
- この点数で出願して意味があるのか
- 二次試験で取り返せる構造なのか
- 不利なまま突っ込むことにならないか
といった、かなり現実的な判断です。
ところが、多くの解説は「勉強法」や「心構え」に寄りがちで、
配点・比率・合格ラインといった出願判断の話が弱い傾向があります。
共通テストができなかった場合に重要なのは、
- 共通テストと二次試験の配点差
- 二次試験で点が動きやすい科目構成か
- 合格最低点がどのあたりにあるか
こうした情報を踏まえて、
「この状況で戦えるかどうか」を冷静に見ることです。
「共通テストできない 二次できる」と検索する人は、
前向きな言葉よりも、判断の材料を求めています。
一般論だけでは埋まらない不安が残るのは、
そこに「今の状況からどう判断するか」という視点が欠けているからです。
ここでしか読めない!独自視点の分析

「共通テストができなかった。でも、二次試験ならまだ勝負できる気がする」
そう感じている一方で、「それは都合のいい思い込みでは?」と自分を疑ってしまう人も多いはずです。
「共通テストできない 二次できる」と検索する人が本当に知りたいのは、
前向きな言葉ではなく、この状況で“戦える条件”がそろっているかどうかです。
ここでは、よくある精神論や一般論から一歩踏み込み、
数字・制度・行動の観点から、逆転の現実性を整理していきます。
大学ごとの「共通テスト比率」と「二次比率」から見た逆転可能性
逆転できるかどうかを考えるうえで、最初に見るべきなのは「努力量」ではありません。
配点構造です。
大学によって、共通テストと二次試験の比重は大きく異なります。
共通テスト比率が低い大学の特徴
共通テストの配点が全体の3〜4割程度に抑えられている大学では、
二次試験で点数を動かせる余地が大きくなります。
このタイプの大学では、
- 共通テストで多少差がついても
- 二次試験の出来次第で順位が大きく入れ替わる
という構造になっています。
「共通テストができなかった」という事実だけで諦めてしまうと、
本来残っている逆転の余地を自分から手放してしまうことになります。
共通テスト比率が高い大学との決定的な違い
一方で、共通テスト比率が高い大学では、
二次試験だけで取り返すのが難しいケースもあります。
重要なのは、
「共通テストができなかったかどうか」ではなく、
その点数差を二次試験で埋められる構造かどうかです。
ここを見ずに、「二次が得意だから大丈夫」と考えるのは危険です。
逆転できる人は、感覚ではなく配点で判断しています。
足切りラインの実態と突破するための最低戦略
「足切りが怖いから、もう無理かもしれない」
これは共通テスト後の相談で、非常によく出てくる不安です。
ただ、足切りについては誤解されている点も少なくありません。
足切り=高得点が必要、ではない
多くの大学で設定されている足切りラインは、
「上位◯%」や「一定の基準点」といった形です。
ここで重要なのは、
合格ラインと足切りラインは別物だということです。
足切りはあくまで、
「最低限、二次試験を受ける資格があるか」を見るための基準です。
共通テスト失敗後に見るべきポイント
足切りを意識するなら、次の点を冷静に確認してください。
- 足切りラインが明示されているか
- 毎年どの程度で設定されているか
- 自分の得点がどの位置にあるか
この確認をせずに、「怖いからやめる」という判断をしてしまうと、
実際には突破できた可能性を見逃すことになります。
足切りは“感覚”ではなく、事実ベースで判断するものです。
共通テスト失敗後に“やってはいけない勉強法”と“本当に伸びる勉強法”
共通テストが終わったあと、焦りから勉強法を間違えてしまう人は少なくありません。
やってはいけない勉強法
共通テスト失敗後にありがちなのが、次の行動です。
- 新しい参考書に手を出す
- 苦手科目を一気に全部やり直そうとする
- 共通テスト対策を引きずった勉強を続ける
これらは「何かやっている安心感」はありますが、
二次試験の得点にはつながりにくいことが多いです。
本当に伸びる勉強法の考え方
この時期に必要なのは、「量」ではなく「方向」です。
二次試験で点を伸ばしている受験生は、
- 配点が高い科目に集中する
- 過去問を使って“取れる形”を固める
- 完璧を目指さず、部分点を積み重ねる
といった判断をしています。
共通テストで失敗したからこそ、
全部を取りに行かない覚悟が、結果につながります。
「共通テストできない 二次できる」と感じている人は、
すでに自分の感覚にヒントを持っています。
大切なのは、その感覚を
配点・制度・行動に落とし込めているかどうかです。
ここを整理できたとき、
「逆転」は希望ではなく、現実的な選択肢に変わります。
共通テストで失敗したときの逆転戦略

共通テストの結果を見て、
「思ったより点が取れていない」
「このまま受験を続けて意味があるのだろうか」
そう感じている人は多いはずです。
「共通テストできない 二次できる」と検索する人の多くは、
すでに現実を直視したうえで、まだ残っている可能性を知りたいと考えています。
ここでは、気合や根性論ではなく、実際に逆転を狙うための具体的な戦略を整理します。
まずやるべき現状分析(科目別・形式別の得点分布チェック)
逆転を狙う第一歩は、「もっと頑張ること」ではありません。
現状を正しく把握することです。
科目別に「失点の理由」を分けて考える
共通テストがうまくいかなかった場合でも、
すべての科目が同じ理由で失点しているとは限りません。
- 英語:時間不足で後半が解けなかった
- 数学:考え方は合っていたが計算ミスが多かった
- 国語:文章量に押されて集中が切れた
このように、知識不足ではなく、形式やスピードの問題で失点している科目も多くあります。
ここを一括りにして「実力不足」と判断してしまうと、
二次試験で使える強みまで見落としてしまいます。
形式別に向き・不向きを整理する
次に確認したいのが、マーク式と記述式の相性です。
- マーク式だと迷って点を落とす
- 記述だと途中までの考え方で点がもらえる
- 自分の言葉で説明する方が力を出しやすい
こうした傾向があるなら、
共通テストで伸びなかったこと自体が、二次向きのサインである可能性もあります。
二次試験重視型の大学・学部選び(逆転合格が狙える大学リスト例)
逆転できるかどうかは、努力量よりも出願先の構造に左右されます。
共通テスト比率が低い大学・学部に注目する
二次試験の配点が高い大学・学部では、
共通テスト後に順位が大きく動くケースがあります。
たとえば、
- 共通テスト:3〜4割
- 二次試験:6〜7割
といった配点構造の場合、
二次試験での出来が合否を左右しやすくなります。
「共通テストができなかった=不利」ではなく、
二次で取り返せる余地が残っているかを見ることが重要です。
逆転が起こりやすい学部の特徴
一般的に、次のような学部は二次試験で差がつきやすい傾向があります。
- 記述量が多い文系学部
- 数学・理科の記述が中心の理系学部
- 小論文や論述が評価される学部
これらは、マーク式よりも思考の過程が評価されやすいため、
共通テストが伸びなかった受験生でも戦える余地があります。
二次で勝てる人の学習ルーティン(添削・記述・過去問演習の徹底)
共通テスト後に逆転している人は、
やみくもに勉強量を増やしているわけではありません。
添削を前提にした記述練習
二次試験で重要なのは、「自分では気づけないズレ」を修正することです。
- 答えは合っているが書き方が弱い
- 条件の拾い方が甘い
- 論理のつながりが分かりにくい
こうした点は、添削を受けないと改善しにくい部分です。
自己採点だけで完結させないことが、得点力につながります。
過去問は「解く」より「分析する」
二次対策では、過去問を解くこと自体が目的ではありません。
- どこまで書けば点が入るのか
- どの設問が合否を分けやすいか
- 毎年似た思考を求められていないか
こうした視点で分析することで、
「取るべき問題」と「深入りしない問題」が見えてきます。
完璧を目指さないルーティン
逆転している受験生ほど、
「全部を完璧にする」発想から離れています。
- 配点が高い分野に集中する
- 部分点を積み重ねる
- 伸びにくい科目は維持にとどめる
共通テストで失敗したあとに必要なのは、
努力を増やすことではなく、方向を絞る決断です。
「共通テストできない 二次できる」と感じているなら、
それは根拠のない希望ではありません。
正しく状況を整理し、
戦える大学・戦える方法を選べば、
逆転は現実的な選択肢になります。
科目別・状況別の具体的対策
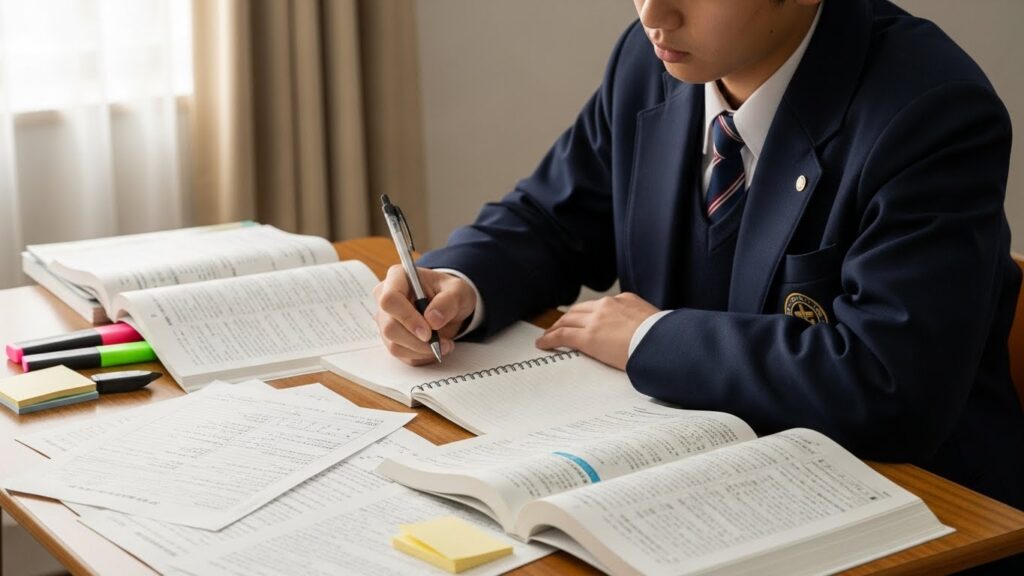
「共通テストでは思うように点が取れなかった。でも、二次試験ならまだ戦える気がする」
そう感じている人の多くは、科目ごとの“ズレ”をうまく言語化できていません。
ここでは、「共通テストできない 二次できる」と感じやすい典型的な科目別パターンを整理し、
共通テストでの弱点を、どう二次試験の得点につなげるかを具体的に見ていきます。
国語 ― 共通テストで失点しやすい人の共通点と二次での活かし方
共通テストの国語が苦手だと感じる人には、ある共通点があります。
共通テスト国語で失点しやすい人の特徴
- 選択肢を最後まで絞りきれない
- 根拠は分かっているのに、正解を選べない
- 時間に追われて読みが雑になる
これは「読解力がない」というより、
選択肢処理とスピードに負荷がかかりすぎている状態です。
二次試験で活かせる強み
二次試験の国語では、
- 本文のどこを根拠にしたか
- どう解釈したか
- どのようにまとめたか
といった思考の過程が評価されます。
共通テストで「ここまでは分かるのに」と感じていた人ほど、
二次試験では文章理解をそのまま答案に反映しやすい傾向があります。
国語は、共通テストで失点していても、
二次で一気に評価が変わりやすい科目です。
英語 ― リーディング速読と英作文の“二刀流”で差をつける
英語は「共通テストができない 二次できる」を最も実感しやすい科目の一つです。
共通テスト英語で伸びにくい理由
共通テストの英語は、
- 語彙力
- 文法力
- 情報処理スピード
を同時に求められます。
そのため、
- 内容は分かるが時間が足りない
- 読めているのに設問処理で落とす
といったケースが頻発します。
二次試験で差がつくポイント
二次試験では、英語の使い方そのものが評価されます。
- 英文を正確に読み取る
- 要点を日本語でまとめる
- 自分の考えを英作文で表現する
特に英作文は、型を身につければ短期間でも安定しやすい分野です。
共通テストで時間に追われていた人ほど、
二次試験の「じっくり考えられる形式」で力を出しやすくなります。
数学・理系科目 ― 共通で凡ミスする人が二次で強みを出す方法
数学や理系科目で共通テストがうまくいかなかった人の多くは、
「分からなかった」のではなく、「ミスが重なった」ケースです。
共通テストで起きやすい失点パターン
- 計算途中でのケアレスミス
- 条件の読み落とし
- 焦りによる確認不足
マーク式では、途中まで合っていても、
最後のミスで一気に失点します。
二次試験で評価されやすい点
二次試験では、
- 途中式
- 考え方
- 論理の流れ
が答案に残ります。
たとえ計算ミスがあっても、
正しい考え方が書けていれば点が入るのが大きな違いです。
共通テストで凡ミスが多かった人ほど、
二次試験では「実力通りの点数」が出やすくなります。
文系科目 ― 資料読み取りが弱い人の逆転シナリオ
社会科目などの文系科目で共通テストが苦手な人は、
資料問題に強いストレスを感じていることが多いです。
共通テスト特有の難しさ
- グラフ・表・文章を同時に処理する
- 問われている視点を瞬時に切り替える
- 消去法に時間がかかる
この形式に合わない人は、
知識があっても点数につながりにくくなります。
二次試験での逆転ポイント
二次試験では、
- 知識を論理的につなげる
- 歴史的背景や因果関係を説明する
- 用語を使って文章でまとめる
といった力が重視されます。
資料処理が苦手でも、
知識を自分の言葉で説明できる人は高く評価されやすいのが特徴です。
共通テストで資料に振り回されていた人ほど、
二次試験では落ち着いて得点を重ねられるケースがあります。
「共通テストできない 二次できる」と感じる背景には、
科目と試験形式の相性があります。
共通テストの結果だけで、自分の可能性を狭めてしまう必要はありません。
科目ごとの特徴を正しく整理すれば、
二次試験で活かせる強みは、まだ十分に残っています。
共通テスト失敗から二次試験本番までの逆転ロードマップ

共通テストが終わった直後、
「この点数で、ここから何をすればいいのか分からない」
「もう時間がない気がして、焦るばかりだ」
そう感じている人は少なくありません。
「共通テストできない 二次できる」と検索している人が本当に知りたいのは、
気持ちの切り替え方ではなく、ここから本番までの“現実的な道筋”です。
この章では、共通テスト失敗後から二次試験当日までを一本の線でつなぎ、
「今、何を優先すべきか」「何をやらなくていいか」を整理します。
1月〜本番までの時間配分(優先順位の決め方)
逆転を狙ううえで、最も重要なのは「残り時間の使い方」です。
ここでの判断が、そのまま結果に直結します。
最初にやるべきは「全部やらない」と決めること
共通テスト後に失敗しやすいのは、
「今から全部を立て直そう」と考えてしまうことです。
残り時間は限られています。
だからこそ、次のように優先順位をはっきりさせる必要があります。
- 二次試験で配点が高い科目
- 得点が伸びやすい分野
- すでに土台ができている内容
逆に言えば、
伸びにくい科目・配点の低い分野は、維持にとどめる判断も重要です。
時期ごとの大まかな考え方
1月後半〜2月前半は、
「解ける形を固める時期」です。
- 記述の書き方を安定させる
- 解答の型を体に覚えさせる
- 失点パターンを減らす
本番直前は、
「新しいことを増やさない時期」に切り替えます。
このメリハリがある人ほど、
二次試験本番で力を出しやすくなります。
模試・過去問・予備校教材の効果的活用術
共通テスト後は、教材の使い方でも差がつきます。
量よりも、「どう使うか」が重要です。
模試は“予測”ではなく“確認”に使う
この時期の模試は、
合否を判断するためのものではありません。
見るべきポイントは次の点です。
- どの科目で点が安定しているか
- どの設問で毎回失点しているか
- 本番を想定した時間配分ができているか
結果に一喜一憂するのではなく、
二次本番に向けた調整材料として使う意識が大切です。
過去問は「解いたあと」が本番
二次試験対策で最も重要なのは、過去問です。
ただし、解いて終わりにしてしまうのは非常にもったいありません。
- どこまで書けば点が入るのか
- 自分の答案は何点くらいになりそうか
- 合格者との差はどこにあるか
ここまで分析して初めて、過去問が意味を持ちます。
点が取れなかった問題よりも、
「取れそうだったのに落とした問題」に注目することが、逆転への近道です。
予備校教材は“絞って使う”
複数の教材に手を出すと、
どれも中途半端になりがちです。
- 信頼できる教材を1〜2冊に絞る
- 二次試験の形式に合ったものを選ぶ
- 繰り返し使うことを前提にする
「やった量」よりも、
「どこまで身についたか」を重視してください。
メンタル管理と集中力維持の方法
(共通テスト後に落ち込まないために)
共通テスト後の時期は、
学力以上にメンタルが結果を左右します。
落ち込みすぎる人ほど逆転しにくい理由
共通テストの結果を引きずると、
- 勉強中も結果が頭から離れない
- 集中が途切れやすくなる
- 自信を失い、手が止まる
こうした状態に陥りやすくなります。
逆転している人は、
結果を忘れているわけではありません。
「今は考えても点数は変わらない」と割り切っているだけです。
気持ちを保つための具体的な工夫
メンタルを安定させるために、次のような工夫が効果的です。
- 勉強内容を細かく区切り、達成感を作る
- 1日の終わりに「できたこと」を確認する
- 不安になったら、配点や過去問に立ち返る
漠然とした不安は、
数字や事実でしか消えません。
本番を見据えた集中力の作り方
二次試験は、長時間の集中が必要です。
日頃から、次の点を意識しておくと本番で崩れにくくなります。
- 時間を決めて集中する練習をする
- 休憩の取り方を固定する
- 本番と同じ時間帯で勉強する
共通テストで失敗した経験は、
決して無駄ではありません。
ここからの行動次第で、
二次試験はまったく別の結果になります。
「共通テストできない 二次できる」と感じているなら、
その感覚を、今日からの行動に落とし込んでいきましょう。
実例から学ぶ「共通テストできないけど二次で合格した人」

共通テストの自己採点を終えたあと、
「思っていたより点が取れていない」
「この結果で二次を受ける意味はあるのだろうか」
そんな不安を抱えている人は少なくありません。
「共通テストできない 二次できる」と検索している時点で、あなたはすでに次を考え始めています。
ここでは、実際の体験例や数字の見方、考え方の切り替え方を通して、今の不安に一つずつ向き合っていきます。
実際の逆転合格体験談(どんな大学・どんな戦略だったか)
共通テストがうまくいかなかった受験生でも、二次試験で評価され合格した例はあります。
共通しているのは、「全部を取り戻そうとしなかった」ことです。
文系・地方国立大学の体験例
共通テストの得点率は6割前後。
判定も厳しく、本人は強い不安を感じていました。
ただ、この大学は二次試験の配点が高く、記述中心の試験でした。
そこで共通テスト後、次のように勉強の方向を切り替えました。
- 二次試験で配点が高い科目に集中する
- 新しい教材には手を出さず、過去問を繰り返す
- 完答を狙わず、部分点を積み重ねる答案を意識する
その結果、二次試験で点を伸ばし、合格ラインに届きました。
共通テストでは評価されにくかった力が、二次試験で形になった例です。
理系学部・数学重視の大学の体験例
共通テストでは英語と理科が崩れ、想定より点数が低くなりました。
一方で、志望校は数学と物理の配点が大きい大学でした。
この受験生が意識したのは、次の考え方です。
- 全問正解を目指さない
- 解ける問題を確実に取る
- 合格最低点から逆算して目標点を決める
気持ちを無理に切り替えるのではなく、「やる範囲を絞る」ことで、落ち着いて対策を進められました。
データから見る“逆転可能ライン”のシミュレーション
共通テストがうまくいかなかった直後は、「もう無理かもしれない」と感じやすいものです。
ただ、配点を数字で見てみると、見え方が変わることがあります。
共通テストより二次試験の比重が大きい場合
たとえば、
共通テスト300点、二次試験700点という配点の大学を想定します。
- 共通テスト6割:180点
- 二次試験7割:490点
合計670点
一方で、
- 共通テスト8割:240点
- 二次試験6割:420点
合計660点
このように、共通テストで点差があっても、二次試験で入れ替わる可能性は十分にあります。
共通テスト後に確認しておきたい数字
感覚だけで判断する前に、次の点を整理してみてください。
- 共通テストと二次試験の配点割合
- 記述問題の比重
- 合格最低点と自分の想定得点との差
これらは大学の募集要項や公式情報で確認できます。
入試制度全体については、文部科学省の公式サイトも参考になります。
数字を整理することで、「まだ届く可能性があるかどうか」が落ち着いて見えてきます。
失敗から学ぶ教訓(共通テスト失敗をバネにする思考法)
共通テストで失敗したあと、どう考えるかによって、その後の行動は大きく変わります。
気持ちが止まりやすくなる考え方
- 自分は本番に弱いと思い込んでしまう
- 判定だけで可能性を決めてしまう
- 何をしても無駄だと感じてしまう
こうした状態になると、勉強に手がつかなくなりがちです。
逆転した人がしていた考え方
逆転合格した人は、共通テストの結果を「終わり」にしていません。
- どこで点を落としたのか
- 二次試験で取り返せる部分はどこか
- 今から点が伸びやすい内容は何か
結果を責めるのではなく、次の行動を決める材料として整理しています。
共通テスト失敗で見えてくること
共通テストがうまくいかなかったことで、次のような点がはっきりします。
- 苦手分野が明確になる
- 時間配分の癖が分かる
- 本番で不安になりやすい科目が見えてくる
これらは、二次試験対策を考えるうえで重要な情報です。
共通テストは終わりましたが、二次試験で動かせる点数はまだ残っています。
今感じている不安は、真剣に受験と向き合っている証拠です。
焦らず、できることを一つずつ整理していきましょう。
共通テスト後から二次試験までの行動ステップ【完全ロードマップ】

共通テストで思うような結果が出なかった場合でも、二次試験までの過ごし方次第で、合否が逆転する可能性は十分にあります。
ここでは、共通テスト後から二次試験本番までに取るべき行動を、段階ごとに整理して解説します。
STEP1 まずやるべき現状整理(今すぐ〜3日以内)
最初にやるべきことは、感情的に焦って勉強量を増やすことではありません。
現在の得点状況と、二次試験で「取り返しやすい科目」を冷静に整理することが重要です。
- 二次試験で配点が高い科目はどれか
- 記述式・論述式で評価される科目は何か
- 共通テストで失点した原因は「実力」か「形式」か
すべての科目を完璧にしようとすると、かえって対策が中途半端になります。
まずは、二次試験で点数につながりやすい部分を明確にしましょう。
STEP2 共通テスト基準の勉強をやめるタイミングを決める(1週間以内)
共通テスト後も、同じ勉強法を続けてしまう受験生は少なくありません。
しかし、二次試験では求められる力が大きく異なります。
- 知識量よりも思考力・表現力が問われる
- 問題数は少ないが、1問あたりの配点が大きい
- 大学・学部ごとに出題傾向が大きく違う
この段階で、
「共通テスト対策の延長」を続けるか
「二次試験向けの対策に切り替えるか」
を判断することが、合否を分けるポイントになります。
STEP3 次試験で点を取るための具体的な対策を固める
二次試験対策では、やみくもに過去問を解くだけでは不十分です。
共通テストとは異なり、二次試験では「どこまで考え、どう表現できるか」が評価されます。
そのため、次の点を意識して対策を進める必要があります。
- 志望校の出題形式に合わせた記述・論述対策
- 採点基準を意識した答案作成
- 過去問を「解く」だけでなく、「分析」する視点
特に独学の場合、
「どこまで書ければ合格点になるのか」
「どの表現が減点されやすいのか」
といった判断が難しく、対策が自己流になりやすい傾向があります。
共通テスト後の限られた期間では、
志望校ごとの出題傾向や二次試験に特化した対策を、効率よく進めることが重要です。
学校の指導だけでは不安が残る場合、
二次試験や志望校別対策に対応した外部サポートを検討する受験生も少なくありません。
一度、整理して確認してみるのも一つの選択肢です。
今の状況から二次試験対策が間に合うか、具体的なサポート内容を確認する
STEP4 出願・併願戦略を最終確認する
勉強と同時に、出願戦略の見直しも欠かせません。
判定だけで判断するのではなく、次の視点を持つことが大切です。
- 二次試験の配点比率
- 共通テストと二次試験の評価バランス
- 自分の得意分野が活かせる大学か
「今の判定=合否」ではありません。
試験構造と自分の強みが噛み合う大学を選ぶことで、
逆転の可能性は大きく広がります。
よくある質問(FAQ)
「共通テストできない二次できる」と検索する受験生の多くは、共通テスト後に不安や疑問を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問に答える形で、戦略の立て方や気持ちの持ち方を整理しました。実際に受験生が悩みやすいポイントを取り上げているので、自分の状況と照らし合わせながら読んでみてください。
共通テストができなくても第一志望を諦めるべき?
結論から言えば、必ずしも諦める必要はありません。第一志望を続けるかどうかは「二次試験の配点比率」と「足切りライン」に大きく左右されます。共通テストの比率が低く、二次試験の比重が高い大学では、二次での得点次第で十分に逆転可能です。
例えば、旧帝大や一部の国公立大学では二次試験の配点が総合点の6割以上を占めるケースがあります。この場合、共通テストで失敗しても二次で巻き返すチャンスがあります。河合塾Kei-Netなどで配点を確認し、「自分の得意科目が二次でどれだけ評価されるか」を基準に判断するのがおすすめです。
第一志望を完全に諦める前に、「配点構成」「過去の合格最低点」「足切りボーダー」を確認し、二次で逆転できる可能性が残されているかを冷静に見極めましょう。
二次試験だけで勝負できる大学はある?
「共通テストできないけど二次で勝負したい」という人にとって気になるのが、この疑問です。国公立大学は基本的に共通テストと二次試験の両方で選抜されますが、二次の配点比率が極めて高い大学・学部も存在します。
また、私立大学の中には「共通テスト利用方式を使わず、個別試験だけで合否を判定する」入試方式があります。つまり「共通テストが苦手でも、自分の得意科目で戦える大学」は確実に存在します。
具体的な大学名や方式は年度によって変わるため、最新の情報はスタディサプリ進路や各大学の入試要項で必ず確認してください。共通テストが苦手でも、出願方式の工夫でチャンスを広げられるのは大きなポイントです。
共通テスト後に戦略を変えるならどのタイミング?
戦略を見直す最適なタイミングは自己採点が出た直後です。共通テストの点数が想定より低かった場合、落ち込む時間を長引かせずに「現実的にどの大学・学部で勝負できるか」をすぐに分析しましょう。
戦略を変える際のチェックポイント
- 第一志望:足切り突破の可能性があるか? 二次配点で逆転可能か?
- 併願校:共通テスト利用か、個別試験重視かを確認
- 安全校:確実に合格できるラインの大学も視野に入れる
また、戦略を変えると決めたら、残りの勉強時間を志望校の二次試験対策に一点集中することが重要です。共通テストの振り返りに時間をかけすぎるのではなく、「これからの努力が点数になる領域」に投資しましょう。
つまり、戦略の見直しは「迷っている時間を最小限にして、即行動に移す」ことがポイントです。共通テスト後の数日間が、その後の合否を大きく左右するといっても過言ではありません。
まとめ
「共通テストできない二次できる」という状況は、決して珍しいことではなく、多くの受験生が経験しています。大切なのは、共通テストの結果に引きずられず、自分の強みを二次試験でどう発揮するかを冷静に考えることです。ここまで解説してきた内容を、最後に整理して振り返りましょう。
- 共通テストができない理由
形式の特殊性(スピード・情報処理力)、マークミスや緊張などが主な要因。 - 二次試験で強みを発揮できる人の特徴
記述力・思考力・論理展開力に優れ、答案を構成する力がある。 - 一般的なアドバイスの限界
「形式に慣れる」「時間配分を改善する」だけでは実践的な解決策になりにくい。 - 本当に必要な視点
出願戦略(配点比率・足切りライン)を踏まえた大学選びが合否を左右する。 - 逆転戦略の基本
現状分析(科目別・形式別)、二次重視型大学の選択、得意科目を武器にする。 - 科目別対策
国語は論理的読解力、英語は速読+英作文の二刀流、数学・理系は答案作成力、文系科目は論述で勝負。 - 逆転ロードマップ
1月以降は二次試験の配点が高い科目に集中、過去問を制限時間内で解く、添削指導を活用する。 - 実例からの学び
共通テストで失敗しても、二次で高得点を取り逆転合格したケースは多い。データ上も「逆転可能ライン」は存在する。 - 思考の切り替え
共通テストの失敗をバネにし、二次試験に集中できる人ほど合格に近づく。 - よくある疑問への答え
第一志望は配点次第で諦めなくてもよい。二次で勝負できる大学は存在。戦略変更は共通テスト直後に行うのが最適。
共通テストでうまくいかなくても、そこからどう立て直すかが本当の勝負です。自分の強みを冷静に見極め、出願戦略と二次試験対策を徹底すれば、逆転合格の可能性は十分に残されています。