「10月から共通テストまで、あとたった数か月…」
そう思った瞬間、胸がぎゅっと締めつけられるような不安に襲われていませんか?
模試の判定は厳しい。点数も思うように伸びない。──
「もう間に合わないのでは?」と焦る気持ち。。。
けれど実は、10月以降こそが点数を一気に伸ばす“伸び期”なのです。
平均で+30〜45点、戦略次第では+100点の逆転も可能。
その方法を知っているかどうかで、合否の行方は大きく変わります。
この記事では、あなたと同じように不安を抱えた先輩たちがどう点数を伸ばし、どう合格をつかんだのかを、具体的な戦略とともに徹底解説します。
「今からでも遅くない」と確信できる内容を、あなたに届けます。
結論:10月から本番までに何点上がる?【平均と最大値】
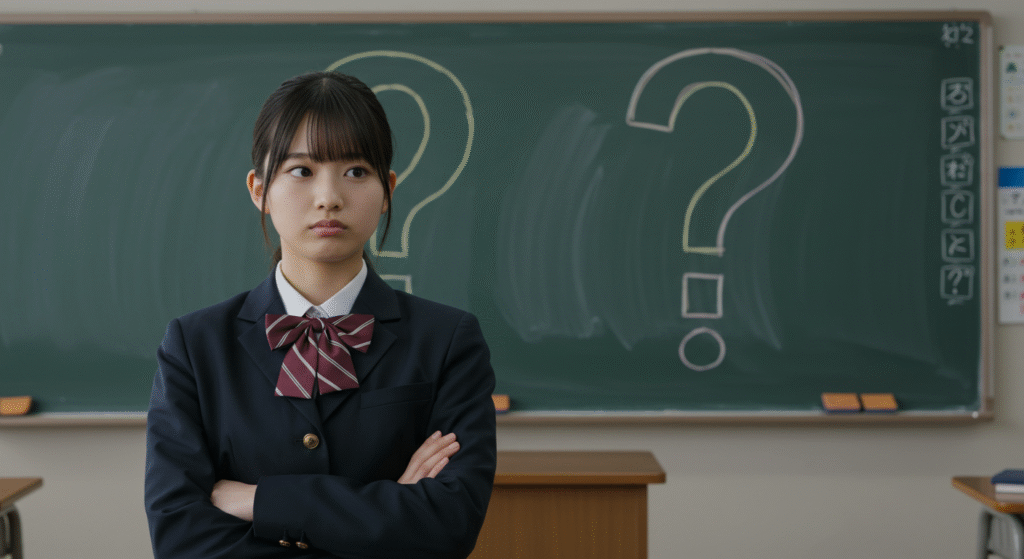
共通テストまで残り3か月となる10月。この時期、多くの受験生が「今からどれだけ点数を伸ばせるのか」を気にしています。実際のデータから見ると、10月から本番までの平均的な伸び幅は30〜45点前後。さらに、条件を満たせば100点以上アップも可能です。
この差を生むのは、単なる勉強量ではなく「得点力に直結する学習戦略」を取れるかどうかです。ここでは、平均値と最大値、そして伸びる人・伸びない人の違いをわかりやすく解説します。
全体の平均伸び幅(+30〜45点前後)
大手予備校や教育機関の模試データを見ると、10月以降に点数が伸びる傾向は明確です。
- 河合塾「全統共通テスト模試」:10月から本番で平均+35点前後(河合塾公式サイト)
- 駿台模試:主要3科目合計で+40点前後(駿台予備学校)
- ベネッセ進研模試:理系平均+45点、文系+30点前後(ベネッセ教育情報サイト)
これらを踏まえると、共通テスト直前期に「+40点前後」は十分に現実的な数字です。特に10月以降は、苦手単元の克服や時間配分の最適化によって“得点力”が目に見えて向上します。
平均が上がる主な理由
- 苦手分野が明確になり、復習の精度が上がる
- 過去問演習を通して「出題傾向」と「時間配分」に慣れる
- 学習サイクルが安定し、得点に直結する学び方へ変化する
つまり、10月からの勉強は「量」ではなく「質」で差がつく時期なのです。
最大で100点以上伸びるケースもある条件
実際に10月模試から本番までに100点以上アップする受験生もいます。そのような成果を出す人には、いくつか共通点があります。
条件①:得点配分の高い科目に集中
英語・数学・国語など、全体の得点を大きく左右する科目を重点的に伸ばすことで、総合点を一気に上げられます。特に英語リーディングは「読解スピード」と「設問慣れ」の練習量で大きく差が出ます。
条件②:週1回の本番形式演習を徹底
10月以降は、週に1回でも構わないので「共通テスト形式(80分通し)」での演習を取り入れましょう。本番の緊張感や時間配分に慣れることが、得点上昇に直結します。
条件③:復習スピードを意識する
伸びる人は、1問の復習に長時間かけません。間違えた理由を3分以内に言語化し、「次にどうすれば取れるか」までを考えます。このスピード感が“伸び率”を左右します。
条件④:生活リズムを「試験本番仕様」に整える
朝型の生活リズム、規則正しい食事、そして十分な睡眠。集中力と記憶力のピークを維持するためには、これらの基礎が不可欠です。模試の日にパフォーマンスを発揮できる人ほど、本番でも安定します。
「伸びる人/伸びない人」を分ける要因
10月以降の成績差は、単なる努力量ではなく「勉強の仕方」と「修正力」にあります。
伸びる人の特徴
- 毎週の模試結果を分析し、弱点を具体的に修正している
- 得点目標を明確に設定(例:「11月までに英語80点」)
- 「間違いノート」などで再現性のある復習をしている
伸びない人の特徴
- 模試を受けっぱなしで、復習を後回しにする
- 苦手科目を避け、得意科目ばかりに時間を使う
- 勉強時間だけ増えても、学習の方向性が曖昧
10月から本番までは「修正力」が最大の武器です。結果を出す人ほど、短いサイクルで課題を改善しています。つまり、勉強時間よりも“改善の回数”が重要なのです。
実践ポイント
- 毎週、科目ごとに「何点伸ばすか」を設定
- 模試の分析シートを作り、ミスの傾向を数値化
- 「勉強時間」よりも「成果の可視化」を重視する
この3つを徹底するだけでも、10月以降の点数は大きく変わります。
読者が知りたい3つの不安と答え

10月を迎えた受験生の多くは、「もう時間がない」「判定が上がらない」「あと何点上げれば合格できるの?」といった不安を抱えています。
この記事では、「共通テスト 10月 から 何点 上がる」と検索する人が抱きやすい3つの悩みを整理し、それぞれに具体的な答えと行動のヒントをお伝えします。
「今からでも逆転できる?」
結論から言えば、10月からでも十分に逆転可能です。
多くの受験生は10月時点で学習の基礎が固まり、ここから「得点力の爆発期」に入ります。
実際、予備校各社の分析によると、10月〜本番(1月)の3か月で平均30〜45点ほど上がる受験生が最も多く、条件がそろえば100点以上アップするケースも確認されています。
(参考:河合塾、駿台予備学校)
逆転できる理由は、「基礎力の上に演習を積むことで、得点に直結する力が一気に伸びる」ためです。
この時期は特に、次の3つを意識すると結果が出やすくなります。
- ①過去問・予想問題を週1回ペースで実施(本番慣れを強化)
- ②ミスの原因を分析して再発防止(復習ノートを活用)
- ③得点源科目を決めて集中(苦手より「伸ばせる科目」に注力)
10月からの勉強は「焦り」ではなく「戦略」で進めることが大切です。
「どの科目が伸びやすい?」
10月以降、特に伸びやすいのは「英語」「国語」「社会(地歴・公民)」です。
英語(リーディング・リスニング)
共通テスト英語は、慣れと時間配分の改善で一気に点が上がります。過去問や模試を通して「読む順番」「設問のパターン」を掴むことで、60点→80点台への上昇も現実的です。
国語(現代文・古文・漢文)
文章構造の読み方を訓練すれば、安定して得点できるようになります。特に現代文は「設問根拠の特定」練習を繰り返すだけで10〜20点アップするケースが多いです。
社会(地理・日本史・倫理政治経済など)
暗記中心の科目は「短期集中で結果が出やすい」ため、10月以降の詰め込みが効果的です。インプットと演習を1セットで回すことが重要です。
一方で、数学や理科は「基礎の定着」と「計算ミス対策」に時間がかかるため、得点上昇にはやや期間を要します。
しかし、「出題傾向を分析して頻出分野に絞る」ことで、着実に+20〜30点を狙うことは可能です。
「判定を1ランク上げるには何点必要?」
判定を1段階上げるためには、一般的に共通テスト全体で+40〜50点が目安です。
| 現在の判定 | 1ランク上げる目安 |
|---|---|
| E → D | +50〜70点 |
| D → C | +40〜50点 |
| C → B | +30〜40点 |
| B → A | +20〜30点 |
この点数差を見て「厳しい」と感じるかもしれませんが、実は科目ごとに狙いを定めれば現実的な数字です。
- 英語リーディングで+15点
- 国語(現代文+古文)で+15点
- 社会で+10点
この3科目だけで、合計+40点。つまり判定を1ランク上げることができます。
10月以降は「どこで何点上げるか」を明確にして、科目ごとの目標を設定することが重要です。
補足
10月以降の勉強で重要なのは、勉強時間よりも得点変化を毎週「見える化」することです。模試・過去問・小テストのスコアをグラフ化し、「努力が数字で見える」状態をつくると、モチベーションが維持できます。
また、模試の判定に一喜一憂するよりも、「共通テスト本番で何点取るか」を最優先に考える姿勢が大切です。10月から本番までの3か月で、戦略的に勉強を積み上げた人こそ、大きな伸びを実現しています。
10月〜本番までの点数の上げ方ロードマップ

共通テストまで残り3か月。焦りが出る時期ですが、実は「ここからの3か月」が最も点数が伸びる時期です。
10月から本番までの勉強を正しい順序で進めることで、平均30〜50点、条件次第では100点以上アップも夢ではありません。
ここでは、共通テスト本番までの「点数を上げるための具体的ロードマップ」を、月ごとにステップ化して解説します。
やみくもに勉強するのではなく、“今の時期に何をすべきか”を明確にして、戦略的に得点を積み上げていきましょう。
10月:弱点分析と出題傾向対策
10月は、最も重要な「分析の月」です。ここで間違った方向に勉強してしまうと、残りの期間の伸びが鈍ります。
まずは模試や過去問を使って「何が分かっていないか」「どの分野が頻出か」を徹底的に可視化しましょう。
具体的な行動ステップ
- 模試・過去問を3回分見直し、間違えた問題をジャンル別に分類
- 「よく出るのに苦手」な単元(例:英語の内容一致・数学の図形問題など)を優先的に復習
- 英語・国語・数学の共通テスト特有の形式に慣れる(河合塾公式サイトで過去問データを確認)
10月はまだ焦る必要はありません。自分の立ち位置を把握し、どの科目で何点上げるかを「戦略的に決める」時期です。
11月:演習量を増やし共通テスト形式にシフト
11月は、「実戦力」を磨く段階です。
ここからはインプットよりも、共通テスト形式の問題演習を中心に進めましょう。
この時期に本番形式に慣れることが、最終的な得点力につながります。
学習のポイント
- 週1回は「共通テスト過去問演習」を通しで解く(時間管理も含める)
- 間違えた問題を「原因別」に分析(時間不足/知識不足/読み違い)
- 理系は計算スピード、文系は読解スピードを意識して演習
また、演習の質を上げるために「復習ノート」を活用しましょう。
ミスの原因を数値化(例:「英文構造の誤読:5回」「選択肢ミス:3回」)して記録することで、弱点を定量的に把握できます。
12月:時間配分と再現性強化
12月は、共通テスト本番に「近い形」での練習がメインです。
模試や予想問題を通して、時間配分・得点の安定化・再現性を高めていきましょう。
この時期の到達目標
ポイント
- 80分の中で「時間配分表」を固定化(英語:20分→25分→35分など)
- 1回の模試で「得点変動±10点以内」に安定させる
- 過去5年分の過去問を「本番同様の条件」で解く
12月に得点が安定してくると、本番で焦らずに実力を発揮できます。
また、この時期は「得点を上げる」よりも「落とさない力」を磨くことも重要です。小さなミスを徹底的に減らすことが、最終的なスコアの底上げにつながります。
直前2週間:暗記科目の“詰め込み”で一気に底上げ
共通テスト直前の2週間は、最後のスパート期間です。
特に社会・理科・古文単語など、暗記中心の科目を徹底的に詰め込むことで得点を底上げできます。
おすすめの取り組み方
- 1日1科目の「総まとめノート」を仕上げる
- 1問1答形式で「口に出して答える」ことで記憶定着率を上げる
- 間違えた問題は翌日に「もう一度だけ復習」して記憶を固定
また、最後の2週間は「睡眠リズム」と「体調管理」も極めて大切です。
生活リズムを共通テスト当日に合わせることで、集中力と判断力を最大限発揮できます。
補足
10月から共通テスト本番までの3か月は、「努力の方向性」がすべてを決めます。
量より質、根性より戦略です。
模試や過去問の点数に一喜一憂せず、“自分が決めた計画をどれだけ再現できたか”を軸に日々の学習を見直しましょう。
正しいステップで勉強を進めれば、10月からでも十分に逆転可能です。
残りの時間を“得点に変える”勉強で、本番に最高の状態で臨みましょう。
科目別:10月から伸びやすい科目と戦略

共通テストまで残り3か月。焦りを感じる時期ですが、ここからでも科目別に正しい戦略を取れば、得点を大きく上げることは十分可能です。
「10月から何点上がるか」を左右するのは、時間ではなく勉強の方向性です。ここでは主要5教科について、10月からでも伸びやすい科目と、その効果的な学習法を解説します。
国語:古典・漢文は短期強化が可能
国語の中でも、特に古典と漢文は10月以降に点数を伸ばしやすい分野です。出題傾向が安定しており、暗記・理解・パターン学習が直接点数に反映されます。
学習ポイント
- 古文単語・文法を1日10〜20語ずつ定着させる
- 助動詞・敬語などの文法は「用法+例文」で覚える
- 過去問を使って「設問の根拠」を意識しながら読む
漢文は「句法・重要語句・返り点」のパターンを30〜50個覚えれば、読解スピードが大幅に上がります。10月からでも+20点前後を狙える教科です。
英語:解き方改善でリーディング時間短縮
英語は「知識量」よりも解き方の改善で点数が上がる科目です。特に共通テスト英語リーディングは、読む順番・時間配分・設問理解の工夫が鍵となります。
時間を短縮するテクニック
- 設問を先に読んで「読む目的」を明確にする
- 全文読破ではなく、必要箇所を「拾い読み」する
- タイトル→設問→本文→選択肢の順で進める
リスニング対策では、スクリプトを使った音読復習が効果的です。1回聞くよりも3回音読する方が定着率が高いと報告されています(ベネッセ教育情報サイト)。
10月からでもリーディングとリスニングの両面を強化すれば、+30〜40点は十分可能です。
数学:典型問題の反復で安定化
数学は「難問対策」よりも典型問題の正答率を上げることが、10月以降の得点アップにつながります。問題傾向が明確なため、反復練習で安定した得点を取れるようになります。
10月以降の勉強法
- 共通テスト過去問・予想問題を1日1分野ずつ解く
- ミスした問題を「原因別」に分類して復習
- 計算スピードよりも「途中式の正確さ」を重視する
特に数ⅡBのベクトル・数列・確率分野は毎年の出題傾向が似ているため、典型問題を繰り返すだけで+20〜30点アップが狙えます。
社会:暗記で得点が伸びやすい科目No.1
社会(日本史・世界史・地理・公民など)は、10月から最も伸びやすい暗記科目の代表です。範囲が明確なため、短期間でも集中学習で得点を大きく上げられます。
効率的な暗記法
- 「1日1テーマ」方式でスモールステップ学習
- 一問一答+図表を組み合わせ、視覚的に覚える
- インプット翌日に「確認テスト」で記憶を固定
社会は努力がそのまま点数に反映されやすく、10月から計画的に暗記すれば、+40〜50点の伸びも可能です。
特に地理・政治経済は統計や制度変更など最新データを確認しておくと安心です(河合塾公式サイト)。
理科:基礎事項の整理で短期得点アップ
理科(物理・化学・生物・地学)は、10月以降に基礎を徹底整理することで急伸する科目です。特に共通テストでは、基礎概念と計算公式の理解が重要です。
学習の進め方
- 過去3年分の出題を分析し、頻出テーマに集中
- 公式や法則を「なぜそうなるか」まで理解する
- 実験問題・グラフ問題は出題パターンごとに整理
理論化学や生物の基本用語整理などは、2〜3週間で効果が出やすい分野です。
基礎を固めれば、本番までに+30点以上アップも十分に現実的です。
何点上げれば合格圏?【スコア別アクションプラン】
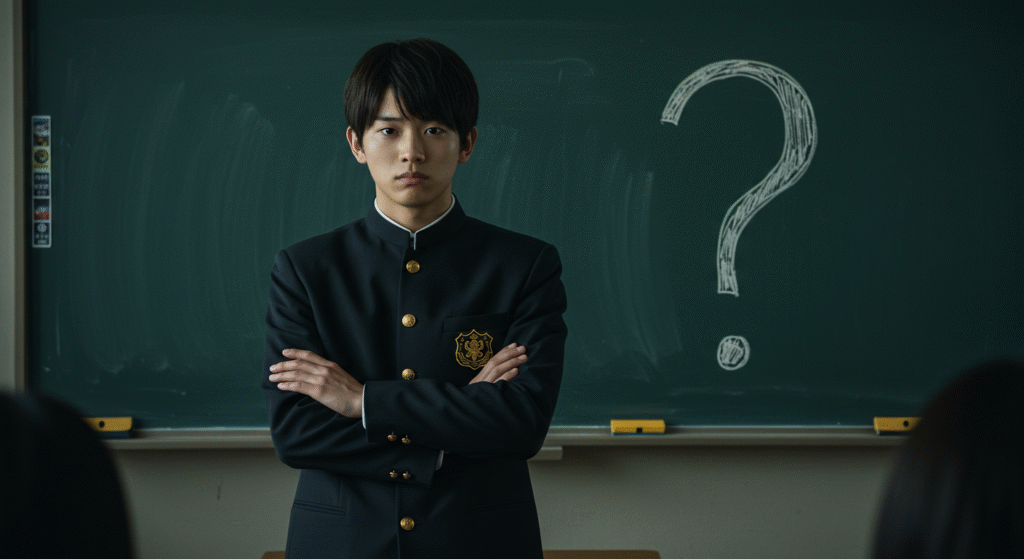
10月の模試を終えて、「あと何点上げれば志望校に届くのか」と不安を感じている人は多いでしょう。共通テスト本番までの3か月は、正しい戦略を取ることでスコアを大幅に上げられる最後のチャンスです。
ここでは、目標までの差が「+20点」「+50点」「+80点以上」の3パターンに分けて、実際に点数を上げるための具体的なアクションプランを紹介します。
+20点で届く志望校:小さな穴を埋める戦略
あと20点差なら、「ミスを減らす」「苦手単元を1つ克服する」だけで十分に逆転できます。すでに基礎はできている人が多く、点数を落としている原因は「ケアレスミス」や「時間配分の乱れ」であることがほとんどです。
具体的な対策ステップ
- ①ミスノートを作り、原因を分類(読み間違い/計算/時間切れなど)
- ②見直し時間を確保(各科目で5分の余白を設ける)
- ③1単元だけ集中して克服(例:英語リスニングPart2、数学の確率など)
また、10月以降の模試は「本番のシミュレーション」として使う意識を持ちましょう。1回の模試で得られるデータ(時間配分・設問傾向・得点バランス)を分析することで、わずか数週間でも安定して+20点前後を伸ばすことが可能です。
(参考:河合塾公式サイト)
+50点必要なケース:得意科目を武器にする戦略
+50点を目指す場合は、全科目をまんべんなく伸ばすのではなく、「得意科目を最大限に伸ばしてスコアを稼ぐ」発想が重要です。得意科目を伸ばす方が効率的で、モチベーションも維持しやすいからです。
実践プラン
- ①得点効率の高い科目を選定(英語・社会・理科が狙い目)
- ②「週ごとの目標点数」を設定し、進捗を見える化する
- ③模試や過去問を週1回ペースで通し演習(本番感覚を磨く)
たとえば、英語リーディングで+15点、社会で+25点、国語で+10点というように、科目ごとに小さな上乗せを積み重ねれば、合計+50点は十分現実的です。
さらに、勉強の比率を「演習6:復習3:分析1」とし、問題演習の中で得点力を磨くことが効果的です。復習では「なぜ間違えたのか」を言語化して、同じミスを防ぐ仕組みを作りましょう。
(参考:ベネッセ教育情報サイト)
とはいえ、「得意科目を軸に伸ばす戦略」が最も効率的だと分かっていても、
- どの科目をどこまで伸ばせば良いのか判断できない
- 自分の勉強法が本当に合っているのか不安
- 計画を立てても途中で崩れてしまう
こうした不安や悩みを抱える受験生は少なくありません。そこで、10月以降の成績を大きく伸ばしたい人に選ばれているのが、オンライン指導の「メガスタ(オンラインのメガスタ)」です。
■ メガスタが“+50点アップを狙う受験生”に向いている理由
- 1対1の完全個別指導で、得点効率の高い科目を一緒に選び、伸ばすべき内容を明確にできる
- 1対5の少人数授業も選べて、質問しやすく、コスパも良い
- 総合型選抜・推薦入試にも強く、志望理由書や面接、小論文までまとめてサポート
- 大学の採点基準に基づいたカリキュラムで、「合格点に届く勉強」に集中できる
- すべてオンラインで完結するため、通塾時間ゼロで時間を最大限に活用できる
- 他塾よりも授業料が抑えめで続けやすい
「あと50点をなんとか伸ばしたい」「効率的な勉強方法をプロに見てもらいたい」という受験生にとって、メガスタは得点戦略と日々の学習を伴走してくれる心強い存在です。
+80点以上必要な場合:捨て科目と伸ばす科目の割り切り
+80点以上の大幅なスコアアップを狙う場合、すべての科目を完璧に仕上げるのは非現実的です。ここで重要なのは、「伸びやすい科目に絞って集中投資」をする戦略的な割り切りです。
スコア逆転のための3ステップ
- ①得点配分の高い科目に集中(英語・数学・国語)
- ②暗記科目(社会・理科)は短期詰め込みで底上げ
- ③苦手科目は「守り」に回す(50〜60点で安定を目指す)
例えば、英語+30点、社会+30点、国語+20点のように得点配分を明確にすれば、全体で80点の伸びが見えてきます。
また、この段階では「どれだけ伸ばせるか」ではなく、「どの科目で点を取るか」が合否を分けます。得意科目を武器にする戦略と、苦手科目を最小限に抑える戦略を両立させることが成功の鍵です。
模試の点数や判定はあくまで「途中経過」です。本番で最大限のパフォーマンスを発揮するために、今の段階で学習の優先順位を見直しておきましょう。
実際に10月から点数を伸ばした先輩の事例

「10月からでも本当に点数は上がるの?」「E判定から逆転できる人ってどんな勉強をしていたの?」――そんな疑問を持つ受験生は多いです。
ここでは、実際に共通テストで10月から本番までに点数を伸ばした先輩たちのリアルなケースを紹介します。
成功例だけでなく、伸び悩んだケースも取り上げることで、「どんな勉強法が効果的だったのか」「なぜ伸びなかったのか」を具体的に理解できます。
模試E判定から本番で+100点の成功例
まず紹介するのは、10月の共通テスト模試でE判定(得点率52%)だったAさんの事例です。Aさんは国公立志望で、共通テスト本番では+102点アップ(得点率約68%)を実現しました。
取り組んだ内容
- 10月:苦手の数学ⅡBを徹底分析。間違いノートを作成し、典型問題を5回以上反復。
- 11月:英語のリーディングで設問先読み練習を導入。1日2題ペースで過去問を演習。
- 12月:週1回、共通テスト本番形式の通し演習を実施。時間配分の固定化に集中。
特に効果が大きかったのは、「自分専用のミスノート」と「週1の通し演習」でした。
Aさんは「勉強時間を増やすより、ミスの原因を減らすことに集中した」と話しています。
その結果、英語リーディングで+28点、数学で+35点、社会で+40点と、総合で100点以上の伸びを達成しました。
このように、10月以降は「弱点克服」よりも“得点力を上げるための分析力”を磨くことが成功の鍵になります。
判定を1ランク上げた標準的な伸び例
次は、10月模試でD判定だったBさんのケース。共通テスト本番では+45点アップし、C判定→B判定相当の得点に到達しました。
このケースは、共通テスト受験生の中でも「最も再現しやすい伸び幅」の代表例です。
行った対策と工夫
- 苦手克服に時間をかけすぎない:社会(日本史B)の暗記を優先し、苦手な数学は“基礎問題だけ”を徹底。
- 演習重視の勉強法:「問題演習7:復習3」の比率を意識。
- 時間配分の安定化:模試ごとに「1問あたりの時間」を記録して改善。
Bさんは「新しい教材には手を出さず、今ある問題集を何周もやった」ことを意識したといいます。
11月下旬の模試では、英語・社会・国語の3教科で平均15点ずつアップ。結果として志望校の合格圏に到達しました。
このケースが示すのは、10月以降は「教材を増やさず、使いこなす」方が圧倒的に効率的ということです。
複数の教材に手を出すより、1冊の問題集を5回繰り返した方が記憶定着率が高いという研究もあります(ベネッセ教育情報サイト)。
最後まで伸び悩んだ失敗例と原因
最後に紹介するのは、10月以降も伸び悩んだCさんのケースです。
Cさんは10月時点でD判定、勉強量は多かったものの、最終的に共通テスト本番では+15点の微増にとどまりました。
失敗の原因
- ①勉強量は多いが方向性が不明確:「とりあえず勉強する」が習慣化していた。
- ②模試の復習をしていない:結果を見て一喜一憂するだけで、原因分析が不十分。
- ③得意科目を伸ばすより苦手克服に時間を割きすぎ:結果的に全体のバランスが崩れた。
10月以降は、時間よりも「戦略の精度」が問われます。Cさんのように、努力量があっても方向性が定まっていないと、点数は思うように伸びません。
特に模試の結果を「やりっぱなし」にするのは避けましょう。1回の模試から得られるデータ(時間配分・正答率・分野別傾向)を整理すれば、次の勉強に直結します。
この点を意識するだけで、点数の伸び率が大きく変わることが多いのです。
成功した先輩たちに共通しているのは、「勉強量よりも方向性」を重視した点です。
10月からの3か月は、闇雲な努力ではなく、データをもとにした戦略的学習こそが最大の伸びを生みます。
直前期でも効く!即効性のある勉強法
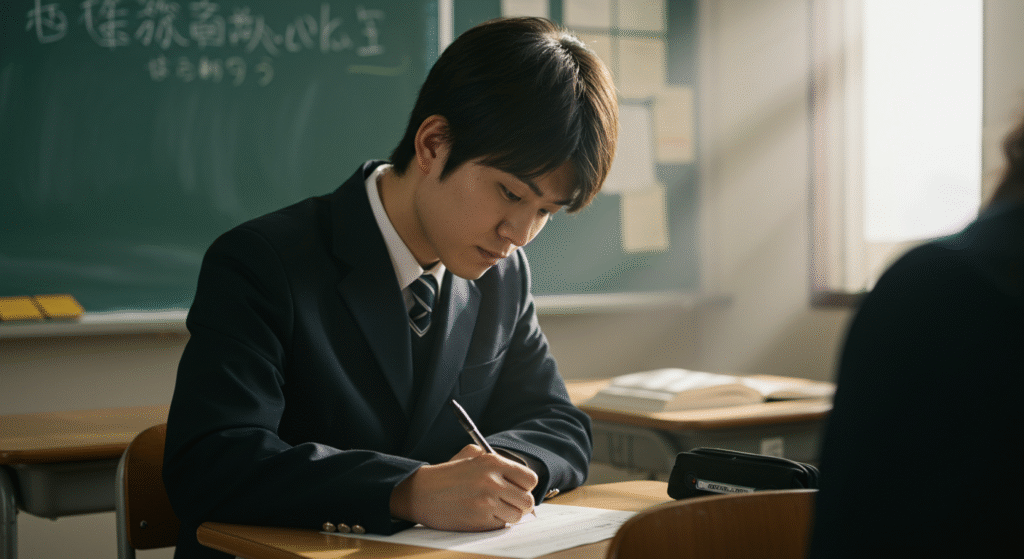
「共通テストまであと少し…」「今からやっても間に合うの?」という不安を抱く10月以降の受験生へ。実はこの時期こそ、勉強法を変えるだけで短期間でスコアを大きく上げることが可能です。
特に共通テストは、思考力よりも「時間配分」「定着の質」「弱点の切り捨て方」で点数が変わる試験です。ここでは、10月以降でも即効性のある勉強法を3つ紹介します。
時間配分のテンプレ(英語・国語・数学・社会・理科)
共通テストは「時間との戦い」と言われるほど、時間配分の最適化が得点を左右します。どの科目も“1問にかけすぎない”意識が大切です。以下は平均的な高得点者の時間配分テンプレートです。
英語(リーディング)
- 第1~2問(語彙・文法):10分
- 第3~4問(中編読解):20分
- 第5~6問(長文読解):40分
- 見直し:5分
最初から満点を狙うより、「どこで取るか」を明確に。設問先読みと根拠読みをセットで訓練すると安定します。
国語
- 現代文(評論・小説):35分
- 古文+漢文:35分
- 見直し:10分
最初に現代文を片方だけ解き、集中力が落ちる前に古文・漢文へ移る「前半分割型」もおすすめです。
数学(ⅠA・ⅡB)
- 小問集合(ⅠA・ⅡB前半):25分
- 大問(後半応用):45分
- 見直し:10分
「1問に3分以上かけない」をルール化。難問にこだわらず、解ける問題から順に確実に取る姿勢が重要です。
社会・理科
- 全体を1周:20分
- 迷った問題を再確認:10分
- 残り時間で精査:10分
全問を最初から順に解くのではなく、「確実に取れる問題から回収」するのが得点安定のコツです。
(参考:河合塾公式サイト・ベネッセ教育情報サイト)
暗記カード・一問一答の活用法
10月以降は「新しい知識を増やす」よりも、「覚えたことを確実に出せる」状態にするのが最優先です。そのためにおすすめなのが、暗記カードや一問一答形式の反復学習です。
暗記カードを最大限活かす3ステップ
- ①1枚1テーマ化:カード1枚につき1知識(例:日本史「享保の改革=徳川吉宗」)に絞る
- ②赤シートより音読:声に出すことで記憶定着率が約1.5倍に向上
- ③1日2周ペース:朝・夜に1回ずつ見直すだけで暗記効率が大幅UP
また、間違えたカードだけを翌日に復習する方式(いわゆる「間隔反復」)を使うと、3日で8割以上の定着が可能になります。
暗記アプリを併用する場合は、スマホでの隙間時間活用も効果的です。移動中や休憩時間に1セット5分程度行うだけでも、積み重ねで大きな差が生まれます。
誤答ノートの“原因別ラベル化”で弱点潰し
共通テストで最後まで伸びる人の共通点は、「自分の間違いの原因を分析して再発を防ぐ」ことです。単に間違いを集めた誤答ノートではなく、「原因別ラベル化」を行うことで弱点が明確になります。
原因別ラベル化の具体例
- ①理解不足:「知識が曖昧」「原理を理解していない」
- ②読解ミス:「設問を読み飛ばした」「キーワードを誤解」
- ③時間不足:「解答途中で時間切れ」「見直し未実施」
間違いの種類をラベルで分類することで、「次に同じ失敗をしないための具体策」が立てやすくなります。
たとえば「読解ミス」が多ければ、問題を解く前に設問にマーカーを引く。「時間不足」なら、1問ごとの目安時間を設定するなど、改善の方向性が明確になります。
誤答ノートは“反省記録”ではなく、“次の得点を上げるためのデータベース”です。10月以降は、新しい問題を増やすよりも、過去の間違いを再発させない習慣をつくることが、最もコスパの高い勉強法です。
よくある質問(FAQ)
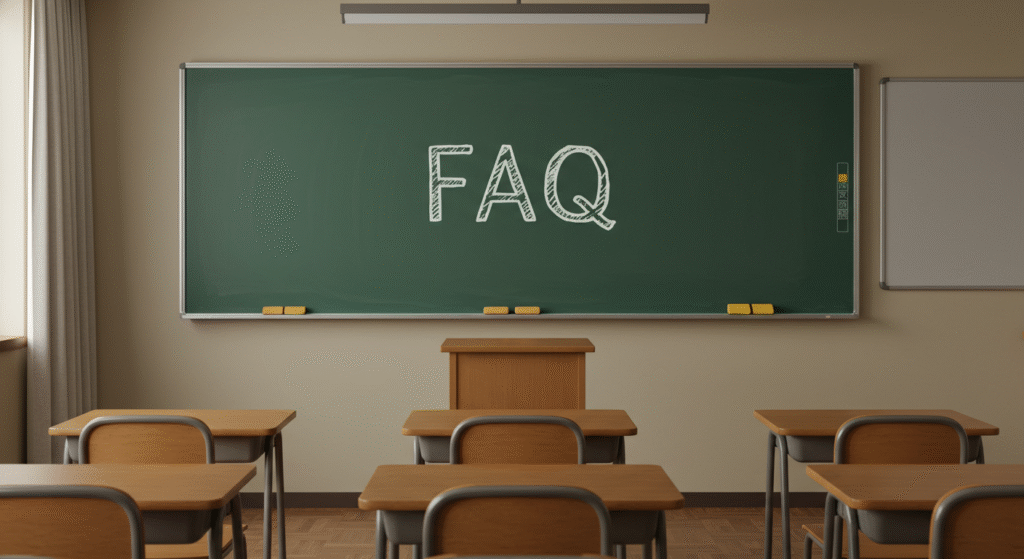
共通テストまで残りわずかとなる10月。模試の結果に落ち込んだり、出願を迷ったりする受験生は多くいます。ここでは、「共通テスト 10月 から 何点 上がる」と検索する人が抱きやすい3つの疑問に、実際のデータと経験をもとに答えていきます。
模試より本番の方が点数が高くなるって本当?
結論から言えば、多くの受験生は本番の方が点数が上がります。
大手予備校(河合塾・駿台・ベネッセなど)の分析によると、10月〜12月の模試から共通テスト本番までに、平均で30〜45点ほどアップする傾向があるとされています。
この理由は2つあります。
① 本番前に「形式慣れ」が進む
10月の模試段階では、まだ共通テスト特有の形式(読解量の多さ・選択肢の紛らわしさなど)に慣れていない受験生が多いです。
しかし12月〜1月にかけて過去問演習を重ねることで、問題パターンが身体に染み込み、本番では自然と反応できるようになります。
② 直前期の“集中力ブースト”が起こる
本番前の緊張感や集中状態が、短期間でのスコア上昇につながるケースも多いです。いわゆる“試験本番特有の覚醒”とも言われる現象で、模試では出せなかった得点力を発揮する人が少なくありません。
ただし、「本番で上がるだろう」と油断するのは危険です。あくまで、「本番で上がる人は、その直前期に演習を重ねた人」であることを忘れずに。
(参考:河合塾公式サイト/ベネッセ教育情報サイト)
10月からでも国公立を目指せる?
答えは「目指せる」です。
ただし、現時点での点数や志望校のレベルに応じて、戦略を切り替える必要があります。
ケース①:現在の得点率が60〜65%前後
この層は国公立に最も現実的に手が届くラインです。
苦手科目を底上げしつつ、得意科目で安定して高得点を取れるようにすれば、残り3か月で共通テスト全体の得点率を70%以上に上げることも可能です。
ケース②:得点率が50〜55%前後
ここからでも逆転は可能です。
共通テストは「配点の高い主要科目(英語・数学・国語)」で一気に伸びる構成になっています。英語リーディングで+20点、数学で+15点、社会で+10点など、重点的に対策すれば合計で+45点の上昇も現実的です。
実際、10月からの戦略変更でE判定→C判定、C判定→B判定に上げた受験生も多くいます。
重要なのは、志望校のレベルを下げる前に「得点配分と伸びやすい科目」を見直すことです。
判定が悪くても出願すべき?
10月の模試でD判定・E判定が出ると、「もう無理かも」と感じる人も多いですが、出願を諦めるのは早すぎます。
共通テストは、他の試験と比べても「本番で点が伸びる試験」です。
実際、河合塾の分析では、10月の模試から本番にかけてE判定だった受験生のうち、約3割がC判定相当まで上昇したというデータもあります。
出願を決めるときの考え方
- ① 判定は「現時点のスナップショット」でしかない。
- ② 合格可能性は「残り期間での伸び代」に比例する。
- ③ 出願校を分散させることでリスクを抑えられる。
特に国公立志望の場合、前期・後期・共通テスト利用など複数の出願枠を活用することで、リスクを最小限にしながら挑戦できます。
判定が悪いからといって、「諦める=合格の可能性を0にする」こと。
逆に出願して努力を続ける限り、合格の可能性は残ります。出願とは「未来に可能性を残す行動」なのです。
10月からでも、努力の方向を変えればまだまだ点数は上がります。大切なのは、数字だけでなく「伸びる余地」を信じて、行動を続けることです。
まとめ 10月からの伸びは“戦略次第で最大化できる”
「共通テスト 10月 から 何点 上がる」と検索する受験生は、残りの時間でどれだけ点数を伸ばせるのか、不安と期待の入り混じった気持ちを抱えています。
結論から言えば、10月以降でも正しい戦略を選べば点数は大きく伸びるのです。
平均は30〜45点だが、戦略と実行で+100点も可能
過去の模試データや受験体験談を分析すると、10月から本番までの平均的な伸び幅は+30〜45点。
この数字は「直前期でも伸びる」という安心材料であると同時に、戦略を誤れば「せっかくの伸びしろを活かせない」リスクも示しています。
しかし、実際には+100点以上伸ばした受験生も少なくありません。
社会や理科基礎、古典・漢文など暗記効率が高い科目に集中投資し、さらに時間配分や解き方の改善を徹底した結果、大幅な逆転劇を実現しています。
つまり、10月からでも「やり方次第」で伸び幅は無限に変わるのです。
科目別の特性を理解して集中投資すべき
限られた時間で最大の得点を狙うには、科目ごとの伸びやすさを理解して戦略的に投資する必要があります。
- 国語(古典・漢文):短期暗記で+15〜25点が狙える
- 英語:時間配分改善や解き方改革で+10〜15点
- 数学:典型問題の徹底反復で失点防止、+10〜20点
- 社会:一問一答を回せば+20〜30点の爆伸び
- 理科基礎:公式暗記と典型問題演習で+10〜20点
これらを合計すれば、+60〜100点の伸びも十分現実的。
「全部を完璧に」ではなく、伸ばせる科目に時間を投資する割り切りが、最後の数か月の勝敗を分けます。
不安は行動に変え、残り期間を“伸び期”にする
10月以降に最も大事なのは、不安を行動に変えることです。
「模試の判定が悪い」「まだ基礎が不安」と悩むのは自然ですが、悩んでいるだけでは点数は1点も上がりません。
- 不安①「本当に逆転できるのか?」 → 行動:「暗記科目に集中し+20点積み上げ」
- 不安②「時間が足りない」 → 行動:「時間配分テンプレを徹底し取りこぼしを防ぐ」
- 不安③「判定が低い」 → 行動:「+15〜20点で判定は1ランク上がる」と理解して粘る
不安の裏側には必ず「行動に変えられるヒント」があります。
10月以降は不安を味方に変え、“伸び期”として走り抜けた人が合格を掴むものです。
- 10月からでも点数は伸びる
模試データから平均+30〜45点の上積みが確認されており、判定を1ランク上げるには十分な数字。 - +100点以上の逆転も可能
社会・理科基礎や古典漢文など暗記系を集中強化し、解き方改善や時間配分を徹底すれば大幅なスコアアップが実現できる。 - 不安に直結する3つの答え
「今から逆転できる?」→可能。
「どの科目が伸びやすい?」→暗記科目と形式対策科目。
「判定を上げるには何点必要?」→15〜20点で1ランク上昇。 - 点数を伸ばす4ステップロードマップ
10月=弱点分析と出題傾向の把握。
11月=共通テスト形式で演習量を増やす。
12月=時間配分と得点の安定化。
直前2週間=暗記科目の詰め込みで得点底上げ。 - 科目別の伸び幅目安
国語(古典・漢文):+15〜25点
英語:+10〜15点
数学:+10〜20点
社会:+20〜30点
理科基礎:+10〜20点 - 必要点数別アクション
+20点=小さな穴を埋めて合格圏へ。
+50点=得意科目を武器に大幅加点。
+80点以上=捨て科目を決め、伸びやすい分野に集中。 - 成功例と失敗例の違いは戦略
成功者=暗記科目集中+誤答分析+時間配分改善。
失敗者=全科目に手を広げ、中途半端で終わった。 - 直前期は即効性ある方法を重視
時間配分テンプレで取りこぼし防止。
暗記カードや一問一答で詰め込み。
誤答ノートを原因別に整理して弱点克服。 - 判定に振り回されない
模試より本番は+30〜45点上がる傾向。
10月からでも国公立逆転は可能。
D判定やE判定でも出願は諦めるべきではない。 - 結論
「共通テスト 10月 から 何点 上がるか」という不安の答えは、戦略次第で大きく伸ばせる。
残り期間を“伸び期”と捉え、不安を行動に変えることが合格への最短ルートになる。
