「あと偏差値5上げれば合格できるのに──」
その小さな差が、志望校との距離を大きく変えます。
模試の判定でC判定やD判定を見て「もう無理かもしれない」と思ったことはありませんか?
でも偏差値5の差は、全国順位で数万人規模の変化。
つまり、あと少しの工夫で一気に合格圏に近づける可能性があります。
本記事では、競合サイトには載っていない“具体的な戦略と習慣”を徹底解説。
今日から実践できる方法で、あなたの偏差値を確実に+5へ導きます。
この記事で分かること(簡易チェックリスト)
・偏差値+5を達成するための基本戦略(分析→演習→スケジュール)
・科目別の具体的な伸ばし方(英語・数学・国語・理社)
・短期間で差をつける+αの工夫(ケアレスミス対策・朝活・誤答ノート)
・直前期でも成果を出す戦略と、やる気を維持するメンタル法
偏差値を「5」上げるには?大学受験生が知るべき基本戦略

「偏差値を5上げたいけど、どうすればいいのかわからない」
「1ヶ月、2ヶ月で本当に上がるの?」
そう感じている大学受験生は多いでしょう。
結論から言うと、偏差値5アップは正しい方法であれば十分に可能です。
ポイントは「勉強の質」と「継続の仕組み化」。努力の方向を少し変えるだけで結果が大きく変わります。
ここでは、偏差値5上昇を実現するための基本戦略を、仕組み・時間・心理の3つの観点から解説します。
偏差値の仕組みと「5」上げる意味
偏差値とは、テストの平均点を基準に「自分が全体のどの位置にいるか」を示す数値です。
平均を50としたとき、偏差値55なら上位約30%、60なら上位約15%に入ります。
つまり、偏差値を5上げるだけで全国順位が大きく変化します。
たとえば、全国10万人規模の模試で偏差値55の人は上位約3万人前後。
そこから60になると上位約1万5千人に入り、実に半数以上のライバルを抜く計算です。
この変化が、大学受験における「C判定からB判定へ」「安全圏外から射程圏内へ」といった逆転の要因になります。
偏差値の算出方法や分布については、ベネッセ教育情報サイト の「模試の偏差値とは?」でも詳しく説明されています。
偏差値5アップに必要な勉強時間の目安
偏差値を5上げるには、どのくらいの時間が必要なのでしょうか。
これは現在の学力や目指す大学にもよりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 期間 | 総学習時間(目安) | 1日あたり |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 約100〜150時間 | 約3〜5時間 |
| 3ヶ月 | 約300〜400時間 | 約4〜5時間 |
| 6ヶ月 | 約600時間以上 | 約3時間前後 |
時間よりも「質」を意識しよう
勉強時間を確保しても、内容が伴わなければ結果は出ません。
重要なのは「インプット→演習→復習」の循環を作ることです。
効果を最大化する3つの学習法
- インプット3:演習6:復習1の黄金比
知識を入れる(3)よりも、問題演習(6)と復習(1)を重視する。
演習中心にすることで「解ける力」がつき、実践スピードが向上します。 - ミスノートで弱点を可視化
間違えた問題の原因を「知識不足」「ケアレスミス」「理解不十分」に分類して記録。
自分の弱点が明確になると、効率的に復習できます。 - 小目標を1週間単位で設定
「1週間で英単語300個」「古文単語100個」など短期ゴールを決め、達成体験を積み重ねましょう。
検索する人が抱えている悩み(時間不足・方法迷子・やる気低下)
「偏差値5上げるには」と検索する人の多くは、
“努力しているのに結果が出ない”という共通の悩みを抱えています。
その背景には、次の3つの要因があります。
① 時間が足りない
学校や部活で忙しく、勉強時間を思うように確保できない。
この場合、スキマ時間の使い方がカギです。
通学中や休み時間を「暗記科目専用タイム」にすることで、1日1時間分の差が生まれます。
おすすめは、スマホアプリでの単語学習。
特に『ターゲット1900アプリ』や『古文単語315アプリ』のように音声付きのものは、移動中でも効率的に記憶を定着させられます。
② 方法が定まらない
「何をやればいいかわからない」「勉強法がコロコロ変わる」
この迷いが成果を遅らせる最大の原因です。
大切なのは、自分に合った勉強法を見極めること。
例えば、同じ参考書でも
- 「反復型(繰り返して覚える)」が得意な人
- 「理解型(仕組みを整理して覚える)」が得意な人
では最適な勉強の順番が違います。
自分の学習タイプを分析し、効率の良い方法を固定化しましょう。
分析には、Z会やスタディサプリなどの学習タイプ診断サービスを活用するのもおすすめです。
③ やる気が続かない
頑張ってもすぐに成果が出ない時期は、どうしてもモチベーションが下がります。
ここで重要なのが、「行動習慣の仕組み化」です。
- 朝起きてすぐ問題集を1問解く
- スマホを触る前に単語を5個覚える
- 夜寝る前に復習ノートを見る
このように“行動のルール化”をすると、意志力に頼らず続けられるようになります。
心理学的にも、小さな行動の繰り返しが大きな成果につながるとされています。
(参考:米国心理学会『Motivation Science』誌)
偏差値5を上げるための3ステップ学習法

「偏差値をあと5上げたいけど、何から手をつければいいのか分からない」
「模試の判定がずっとC判定のままで焦っている」
多くの大学受験生が抱えるこの悩み。
結論から言うと、偏差値5を上げるためには、感情ではなく“戦略”で動くことが重要です。
勉強量を増やすだけでは結果は出ません。
「どこに時間を使い、どこを捨てるか」を明確にすれば、短期間でも十分に偏差値5アップが可能です。
ここでは、偏差値を上げるための具体的な3ステップ学習法を紹介します。
模試の分析から勉強計画まで、「やるべきことが整理される構成」で解説していきます。
ステップ1|現状分析と弱点把握(模試・過去問活用)
最初のステップは、現状を正確に把握すること。
偏差値を上げたい人ほど「とにかく勉強しなきゃ」と焦りがちですが、最短ルートは「自分の弱点を知る」ことです。
模試は“診断書”として使う
模試は単なるテストではなく、「自分の学力を数値化した診断書」です。
結果を見るときは点数だけでなく、どの単元・どの設問形式で落としているかまでチェックしましょう。
- 正答率が高い問題でミス → ケアレスミス、集中力の問題
- 正答率が低い問題でミス → 知識不足または理解不足
- ケアレスミスが多い科目 → 演習量や時間配分の見直し
偏差値を上げるには、「不得意科目を底上げ」よりも「得点源を安定させる」ほうが早く成果が出ます。
過去問分析で“出題傾向”を読む
志望校の過去問を分析することで、出題形式の特徴やよく出る分野がわかります。
「頻出分野 × 自分の弱点」を掛け合わせた範囲から優先的に対策するのがポイントです。
模試や過去問分析の方法は、河合塾Kei-Netでも詳細に解説されています。
ステップ2|インプット3:アウトプット7の黄金比で勉強
次に意識したいのが、「インプットとアウトプットのバランス」です。
多くの受験生は「参考書を読む=勉強」と思いがちですが、実際に偏差値を上げるのは演習(アウトプット)の時間です。
なぜ“アウトプット7割”が最強なのか
学習効率に関する教育心理学の研究では、「人は覚えたことを使うことで記憶が定着する」と言われています。
つまり、「読むだけ」「書くだけ」ではなく、“問題を解いて使う”ことで脳に定着します。
黄金比を実践する具体例
- インプット(3):参考書・授業で知識を理解
- アウトプット(7):問題演習・過去問・模試で知識を使う
- 復習(セット):間違えた問題は24時間以内に再確認
これを1日の学習サイクルに組み込むことで、知識が“使える武器”に変わります。
また、アウトプット中心の勉強は、試験本番の思考スピードも上げる効果があります。
小テスト形式で定着率を高める
自分で「10問テスト」を作り、正答率を毎日記録するのも効果的です。
数字で進捗が見えると、モチベーションの維持にもつながります。
ステップ3|週ごとの逆算スケジュールで計画的に進める
偏差値5アップを実現するには、「計画の立て方」が最後の決め手です。
やみくもに勉強するよりも、“逆算スケジュール”で進めることが成功への近道になります。
まず「ゴールから逆算」する
たとえば、共通テストまで残り3ヶ月とした場合
- 目標偏差値を設定(例:55→60)
- 必要な科目の得点目安を割り出す
- そのために必要な単元・教材をリスト化
- 各週の学習内容を決めて実行
これを行うことで、「何を・いつ・どの順でやるか」が明確になります。
週単位のスケジュールがベスト
日単位で細かく立てるよりも、週単位のほうが継続しやすく修正もしやすいです。
1週間の計画の中で、
- 「進んだ単元」
- 「未完了の項目」
を振り返り、翌週に調整するサイクルを作りましょう。
例:1週間の学習スケジュール(目安)
| 曜日 | 学習内容 | 時間配分 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 学校+復習+演習 | 各2〜3時間 |
| 土曜 | 苦手単元の復習・模試分析 | 約4時間 |
| 日曜 | 過去問・予想問題の演習 | 約4〜5時間 |
スケジュールを守ることよりも、「進捗を見直し、修正する」意識が大切です。
計画は完璧である必要はありません。“柔軟に続ける”ことが成功の秘訣です。
偏差値5を上げるには、膨大な時間や才能は必要ありません。
重要なのは、「現状把握→演習中心→計画実行」の3ステップを回すこと。
この循環ができたとき、偏差値は確実に動き始めます。
科目別|偏差値5アップの具体的アプローチ

「頑張っているのに、どの科目もあと少し点が伸びない」
「効率よく勉強して偏差値を5上げたい」
そんな大学受験生の悩みに共通しているのが、“全科目を同じように勉強している”という点です。
偏差値を5上げるには、科目ごとに戦略を変えることが不可欠です。
ここでは、英語・数学・国語・理科社会の4分野に分けて、短期間で成果を出す具体的アプローチを紹介します。
英語|単語・文法+長文読解を段階的に伸ばす方法
英語の偏差値を上げるには、「語彙・文法・読解」を順番に積み上げるのが鉄則です。
多くの受験生が読解練習に飛びつきますが、語彙と文法が土台にないとスコアは安定しません。
ステップ1:単語と熟語を“最初の武器”にする
英単語は1,500〜2,000語レベルをまず完全に覚えること。
『ターゲット1900』や『システム英単語』を1冊決めて、3周を目標に繰り返すのが効果的です。
覚えたつもりを防ぐために、「朝10分の復習+夜の確認テスト」で定着を強化しましょう。
ステップ2:文法の“型”を理解する
文法は丸暗記ではなく、「なぜそうなるか」を理解することが重要。
特に、品詞の働き・時制・関係詞・仮定法の4分野を重点的に整理しましょう。
参考として、スタディサプリENGLISH の基礎文法講座などを活用すると、苦手分野を効率的に潰せます。
ステップ3:長文は“構文読み”から“内容読み”へ
いきなり全文訳を目指さず、構文(文の骨格)を意識して読むことから始めます。
最初は短文で構文を確認し、慣れたら共通テストレベルの長文を毎日1題。
「毎日少しずつ読む」ことで、英文を日本語に変換せず理解できる“英語脳”が育ちます。
数学|基礎問題の反復からスピード演習へ
数学は“センス”ではなく“型”で伸ばす科目です。
偏差値5を上げるには、基礎の反復→応用演習→スピード強化の3段階が効果的です。
ステップ1:基礎問題で「使える公式」を身につける
難問よりも、まずは教科書レベルの基本例題を完璧にすること。
『青チャート』『Focus Gold』などで、1問ごとに「解法の流れ」を説明できるようにしましょう。
ただ解くだけでなく、「なぜその公式を使うのか」を意識することが理解定着のポイントです。
ステップ2:応用問題で「パターン認識」を鍛える
基礎が固まったら、応用問題で出題パターンを分類。
「数列の和」「二次関数の最大最小」「ベクトルの内積」など、よく出る型を整理してノート化します。
このノートは、試験直前の“最強の武器”になります。
ステップ3:制限時間を設けてスピード演習
時間制限をつけることで、“解ける”から“間に合う”に変わります。
タイマーで計測しながら過去問を解き、解答スピードを磨いていきましょう。
国語|現代文の読解パターン化と古典暗記の効率化
国語は「センス」ではなく「パターン認識」で伸ばす科目です。
特に現代文では、“文章の構造”をつかむ力が偏差値アップの鍵になります。
現代文:設問パターンを分析する
設問文には「傍線部説明」「理由説明」「要約」「内容一致」など、決まったパターンがあります。
それぞれに対応する“解答の型”を覚えることで、読解が安定します。
たとえば「理由を答える」設問では、
- 傍線部の直前後を読む
- 接続詞「だから」「したがって」を探す
- 抽象語を具体化する
という手順を習慣化するだけで正答率が上がります。
古典:暗記は「文法+単語+音読」の3点セット
古文単語帳を使うだけでは不十分です。
文法(助動詞・助詞)を理解し、音読でリズムを覚えることで、文章理解が飛躍的に早くなります。
古文は目で読むより声に出す方が記憶に残りやすいという研究もあります(出典:国立国語研究所)。
理科・社会|短期間で伸ばす暗記+演習法
理科・社会は「暗記教科」と思われがちですが、覚える→使う→定着するの循環を作ることがポイントです。
ステップ1:1テーマを1日で完結させる
長時間同じ科目をやるより、1テーマごとに覚える→確認するサイクルを回した方が定着率が高いです。
「1日1分野」を目安に、スモールステップで進めましょう。
ステップ2:演習で記憶を“引き出す練習”
暗記後すぐに問題を解くことで、記憶の引き出しが強化されます。
特に共通テスト形式の問題集を利用し、「知識→実践→再確認」の流れを毎週繰り返します。
ステップ3:図表・語呂合わせ・動画を活用
地理や生物のようにビジュアルが重要な科目は、視覚記憶を使うと効率が上がります。
YouTubeの教育チャンネルやオンライン講座を活用し、苦手範囲を短期間で補強しましょう。
どの科目にも共通して言えるのは、“やみくもにやらない”ことです。
「弱点を把握 → 型を作る → 継続する」この流れを徹底すれば、偏差値5アップは決して夢ではありません。
他のサイトにない独自視点|+αの工夫で差をつける

偏差値を5上げたいと思っても、「時間がない」「集中できない」「同じミスを繰り返す」といった壁にぶつかる人は多いです。
しかし、成績を伸ばす人は、ただ勉強量を増やすだけでなく、+αの工夫で効率を上げています。
ここでは、成績上位者が実践している「ちょっとした習慣」や「環境の作り方」を紹介します。
この4つを実践することで、偏差値5アップのスピードが格段に早まります。
ケアレスミス対策で「取りこぼし」をゼロにする
偏差値アップを目指すうえで最ももったいないのが、実力があるのにミスで落とすことです。
ケアレスミス対策は、難問を解けるようになるよりも即効性があります。
よくあるミスの原因
- 計算途中の写し間違い
- 問題文の読み飛ばし
- 単位の見落とし
- 選択肢のズレ
これらは「不注意」ではなく、「確認の仕組みがないこと」が原因です。
ミスを減らす3つの習慣
- 解答前に指差し確認
設問条件・単位・符号を声に出してチェックします。 - 解答後30秒の見直しルール
「一度見直す習慣」が、得点安定の最大のポイントです。 - ミス専用ノートを作る
自分の傾向を記録して、同じ失敗を防ぎましょう。
「1回ミスを防げば3点、3回で9点」。この積み重ねが偏差値5アップにつながります。
スマホ依存を断ち切る環境づくり(集中力を奪う最大の敵)
勉強の質を下げる最大の原因は、スマホによる集中力の分断です。
1度通知を見るだけで、集中が戻るまで平均23分かかるという研究があります。
スマホ依存を断ち切る3つの方法
- 物理的に距離を取る
机の上に置かない。勉強中は別の部屋に。 - 使用制限アプリを導入する
「Forest」や「Focus To-Do」などで集中時間を可視化。 - “使わない時間”を記録する
スクリーンタイムを確認して、減った時間を「勉強時間」に変換。
スマホを完全に禁止するのではなく、「使う時間をコントロールする」ことが鍵です。
朝活勉強で効率を最大化する方法
「夜型だから朝は苦手」という人も多いですが、実は朝の学習時間は記憶定着率が最も高い時間帯です。
朝活の3つのメリット
- 睡眠でリセットされた脳は吸収力が高い
- SNSや通知などの誘惑が少ない
- 「1日をスタートで制した」感覚で自信がつく
朝勉強のコツ
- 起きて30分以内に机に向かう
- 英単語・古文単語など「暗記系」に集中
- 朝活専用教材を1冊だけ用意して迷いをなくす
平日1時間の朝勉強を続けるだけで、月に20時間の学習差が生まれます。
その積み重ねが、周りとの差を確実に広げていきます。
+αの工夫でさらに効率を上げる
朝活で“時間の差”をつくれたら、次は“質の差”をつくる番です。
もし「勉強時間は確保できているのに、伸び悩んでいる」と感じるなら、
オンライン個別指導の「メガスタ」を活用してみるのもおすすめです。
- 総合型選抜・推薦入試に強く、準備ゼロからでも合格を目指せる
- 志望理由書・面接対策など“偏差値以外の評価軸”まで徹底サポート
- 1対1指導で苦手科目をピンポイント克服
- 大学の採点基準に沿ったカリキュラムで、確実に点を伸ばす
- オンライン完結で、朝勉強後にそのまま受講も可能
- 他塾よりも安く、家計に優しい料金設定
「朝活×個別指導」で、努力を結果に変える最短ルートをつくりましょう。
オンラインのメガスタ公式サイトを見る
「自分専用の誤答ノート」で弱点を見える化
偏差値を上げる人は、ただ問題を解くだけでなく、「自分のミスをデータ化」しています。
誤答ノートは、あなたの苦手を可視化し、次のテストで確実に得点するためのツールです。
誤答ノートの作り方
- 科目を分けずに1冊にまとめる
見返しやすく、復習効率が高まります。 - “なぜ間違えたか”を具体的に書く
知識不足、焦り、読み間違いなど原因を書き出す。 - 再挑戦日を設定する
「3日後・1週間後・模試前」など、復習タイミングを明記。
記入例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題 | 河合模試 数学ⅠA 第2問 |
| ミスの原因 | 焦りによる符号ミス |
| 対策 | 見直しチェックリストを追加 |
| 再挑戦日 | 3日後・次の模試前 |
誤答ノートは「失点を資産化」する最強の方法です。
繰り返し見直すことで、弱点が“得点源”に変わります。
最後の1ヶ月でも偏差値5は上げられる?
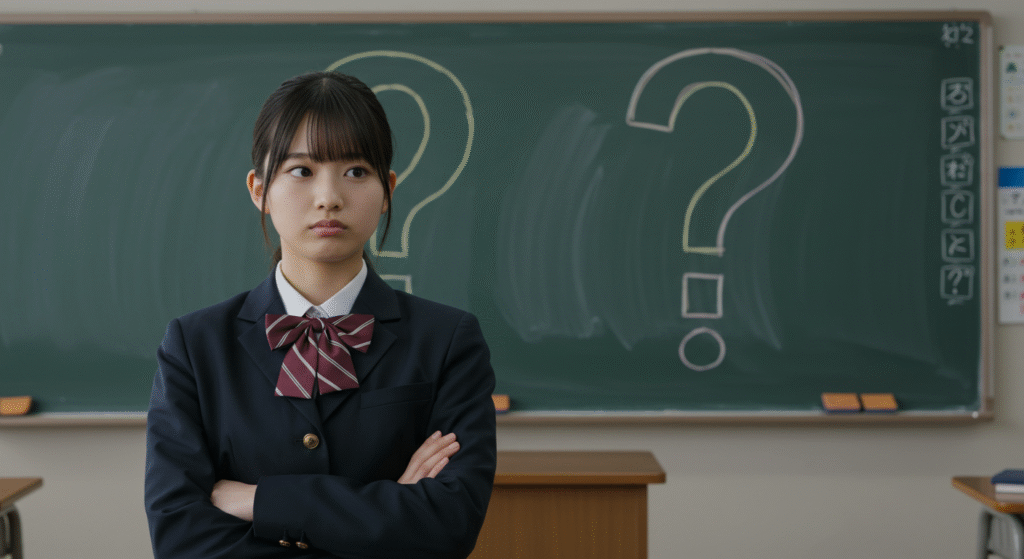
「本番まであと1ヶ月。もう間に合わないのでは?」
そう感じている人こそ、偏差値5アップのチャンスがあります。
なぜなら、この時期は“焦って全体をやろうとする人”と、“戦略的に得点を積み上げる人”で結果が大きく分かれるからです。
1ヶ月あれば、勉強時間にしておよそ100〜150時間を確保できます。
この時間を「正しい方向」に使えば、偏差値を5上げることは十分に可能です。
残り時間が少ない人の戦略(得点源科目に絞る)
短期間で結果を出すには、“やることを減らす”勇気が必要です。
全科目をバランス良く伸ばすのは時間的に不可能。
今からは「得点源にできる科目」を1〜2科目に絞りましょう。
ステップ1:得点効率を見極める
過去の模試データや学校のテストを見て、次のように分類します。
- 伸びしろが大きい科目:あと少しで平均点を超える科目
- 得点源にできる科目:安定して6〜7割取れている科目
この2つに絞って勉強するのが、最短で偏差値を上げるコツです。
ステップ2:弱点補強より「得点安定」を優先
偏差値を上げたい時期に“苦手克服”をしてはいけません。
むしろ、「今できる範囲で確実に点を取る」ことを優先します。
たとえば英語なら「文法問題」「整序問題」、数学なら「典型パターン問題」。
出題頻度が高い問題だけを徹底的に固めるのが効率的です。
ステップ3:1日のテーマを1つに絞る
「今日は英文法の時制」「今日はベクトルの計算練習」といったように、1日1テーマ主義で進めると集中力が途切れません。
限られた時間でも、「1日ごとに1つ成長した実感」が得られます。
失点を減らす“凡ミス撲滅”作戦
直前期は“新しい知識を増やす”よりも、“失点を防ぐ”ことが偏差値アップに直結します。
実際、模試で偏差値50台の受験生が5ポイント上げたケースの多くが、凡ミスをなくしただけです。
よくあるミスのパターン
- 計算の符号を間違える
- 単位や桁をミスする
- 選択肢を1つずらしてマークする
- 問題文の条件を読み飛ばす
こうしたミスは、学力ではなく「確認力」の問題です。
防止のための具体的ルール
- 30秒チェックルール
解き終えたら、必ず30秒だけ見直しに使う。 - “指差し確認”で思考を止めない
設問の条件や単位を指で追うだけで、注意力が維持できます。 - ミス記録ノートを作る
「何を」「なぜ」間違えたかを1行でメモするだけで、同じ失点が激減します。
凡ミスの撲滅は、難問突破よりも早く偏差値を押し上げる実践法です。
本番直前の今こそ、「減点を防ぐ戦い」に集中しましょう。
合格者が実際にやった「直前期の工夫」
偏差値を短期間で上げた合格者たちは、「生活リズム」と「勉強環境」にも工夫をしています。
ここでは、実際に結果を出した人たちの共通点を紹介します。
① 朝型に切り替えて集中力を最大化
朝の時間は脳が最もクリアで、暗記効率が高い時間帯。
共通テストや国公立の試験時間に合わせて、朝7時から集中できる体調リズムを整えておきましょう。
② 「1日の終わりに3行まとめ」
夜、勉強を終えたら「今日やったこと・気づいたこと・明日の目標」を3行でメモします。
これにより、次の日の勉強開始がスムーズになり、迷いがなくなります。
③ 模試や過去問は“復習中心”で活用
解き直しの際は、正解した問題よりも間違えた問題を3回解くのが鉄則です。
「自分の弱点」を“自分専用の教材”に変えることで、短期間でも得点力が安定します。
「もう時間がない」と感じたときこそ、やるべきことを絞り、行動を具体化することが成功への鍵です。
偏差値5アップは、勉強時間の量ではなく、“戦略と集中の質”で決まります。
モチベーションを維持するためのメンタル戦略

「勉強しなきゃ」と思っても、なかなか続かない——。
「偏差値5上げたい」と願っている受験生の多くが、実は“やる気の波”に悩まされています。
偏差値アップには、勉強法だけでなくメンタルの保ち方が大きく関わっています。
ここでは、心理学や教育実践の視点をもとに、「努力を続けられる人の考え方と仕組み」を紹介します。
「小さな成功体験」を積み重ねてやる気を継続
やる気が続かない原因の多くは、「成果がすぐに見えない」ことです。
しかし、人間の脳は“できた”という感覚を得たときに最もやる気ホルモン(ドーパミン)が分泌されるとされています。
成功体験を積む3ステップ
- 1日のノルマを“超小さく”設定する
「英単語を10個覚える」「数学の例題を3問だけ」など、今すぐ終わる目標を立てる。
終えた瞬間に「できた!」という達成感が生まれ、次の行動につながります。 - 勉強を“見える化”する
カレンダーにスタンプを押す、ToDoリストを線で消すなど、達成の視覚化は脳に強い報酬を与えます。 - ご褒美タイムをあらかじめ設定
「ここまでやったら10分スマホOK」「お菓子タイム」と決めると、自然と集中力が続きます。
このように、“やる気を出そうとする”のではなく、“やる気が出る仕組み”を作ることが大切です。
ライバルとの差を意識しすぎないための思考法
SNSや模試の結果を見ると、「自分は全然ダメだ」と落ち込む瞬間がありますよね。
しかし、他人との比較は、モチベーションを削ぐ最大の敵です。
競争ではなく「成長ベース」で考える
偏差値を上げる本当のコツは、「昨日の自分を超える」こと。
他人の結果ではなく、自分の行動の質にフォーカスします。
- 昨日より10分多く勉強できた
- 苦手な単元を1つ克服できた
- 間違いノートを更新できた
こうした「自分比較」を続けると、精神的な安定と集中力が増します。
結果的に、長期的にモチベーションが落ちにくくなるのです。
“ライバルを見るタイミング”を決める
常に比較していると疲れるため、模試の後だけライバルを意識するのが最適です。
模試後に「ここだけは勝っている」「次はこの範囲を追いつこう」と冷静に分析すれば、他人の存在が“刺激”に変わります。
心理学ではこれを「目標的比較(Achievement Goal Theory)」と呼び、適度な競争意識は集中力を高めるとされています。
勉強が続かない時のリセット法(運動・休憩・場所替え)
どんなに気合を入れても、やる気が落ちる日は必ずあります。
そのときに「サボった」と罪悪感を持つのではなく、“リセット”の時間だと捉えましょう。
① 運動で脳をリフレッシュ
短時間の運動には、集中力を回復させる効果があります。
特におすすめは「軽いストレッチ」「5分間の散歩」「階段の上り下り」。
血流が良くなることで脳の覚醒度が上がり、再び集中できる状態になります。
② 15分の“戦略的休憩”を取る
疲れたときにダラダラ休むと、かえって罪悪感が残ります。
そこで、「15分だけ休む」と時間を区切るのがポイントです。
タイマーをかけて机から離れ、深呼吸をして気持ちを切り替えましょう。
③ 場所を変えて刺激を得る
自宅で集中できないときは、環境を変えるのが最短の解決法です。
図書館・カフェ・自習室など、いつもと違う空間で勉強するだけで、脳が“新しい刺激”を受けて集中しやすくなります。
④ 「できなかった日」を責めない
モチベーションは波があって当然です。
大事なのは、次の日に机に戻れるかどうか。
たとえ1日サボっても、「翌日リスタートできた自分」を褒めてあげましょう。
これが、長く走り続けるための最強のメンタル管理法です。
偏差値を上げる勉強法は数多くありますが、続けるための“心の整え方”を知っている人は多くありません。
モチベーションを科学的にコントロールすることで、努力を「続けられる習慣」に変えることができます。
まとめ|偏差値5アップは戦略と習慣で実現できる
偏差値を5上げたいと考える大学受験生の多くは、時間不足や勉強法への迷い、やる気の維持といった課題を抱えています。
しかし、実際に偏差値を伸ばしている受験生は「特別な才能がある人」ではなく、戦略と習慣を味方につけた人です。
今日から始められる行動チェックリスト
偏差値を上げるために必要なのは「大きな努力」ではなく「小さな習慣の積み重ね」です。
以下のチェックリストを、まずは1つでも実行してみてください。
学習習慣
- 模試や過去問の誤答をノートにまとめ、翌日→3日後→1週間後に解き直す
- インプットよりもアウトプット(演習)に学習時間の7割を使う
- 毎週末に「今週の達成度」を振り返り、翌週の計画に反映
時間管理
- 入試日から逆算して週単位の学習スケジュールを作る
- 朝の時間を「暗記・苦手科目専用」に充てる
- 勉強中はスマホを机から遠ざけ、集中を妨げない環境を作る
メンタル戦略
- 毎日「小さな成功体験」を記録する(例:単語30個暗記達成)
- ライバルではなく「昨日の自分」と比較する
- 集中が切れたら短時間の運動や場所替えでリセットする
このチェックリストは「今日からできる行動」に絞っています。
即行動→小さな成功→モチベーション維持という流れを作ることが、偏差値アップの近道です。
まとめ
【学習習慣】
・誤答ノートを作り、翌日→3日後→1週間後に解き直す
・演習7割:暗記3割の学習バランスを徹底
・毎週末に振り返り→翌週計画に修正を加える
【時間管理】
・入試日から逆算し、週単位でスケジュールを作成
・朝の時間を「暗記・苦手科目専用」に設定
・勉強中はスマホを机から遠ざけ、集中環境を確保
【メンタル戦略】
・毎日「小さな成功体験」を記録
・ライバルではなく「昨日の自分」と比較
・集中が切れたら運動や場所替えでリセット
偏差値+5はゴールではなく通過点
偏差値5を上げることは確かに大きな成果ですが、大学受験は「合格」というさらに大きな目標があります。
偏差値+5はゴールではなく、その先にある合格へと続く“通過点”に過ぎません。
視点を広げる
- 偏差値を上げることだけにとらわれず「入試本番で合格点を取る」ことを最終目標にする
- 合格可能性判定に一喜一憂せず、「伸びた部分」と「伸ばすべき部分」を冷静に分析する
- 偏差値5アップを達成した後は、さらに次の課題(得点力・答案作成力)に挑戦する
未来へのつながり
- 偏差値アップの過程で身につけた「計画力」「習慣化」「集中力」は大学進学後も武器になる
- 今の努力は「受験のため」だけでなく「将来の自分の成長」につながる
偏差値+5は目的地ではなく、スタートラインを前に進めるための切符。
そこに到達したら、さらに合格点・合格圏を突破するための新しい戦略を組み立てることが重要です。
まとめ
・偏差値+5は最終ゴールではなく、合格に近づくための通過点
・合格点を取ることを最終目標に据える
・伸びた部分と課題を分析し、新しい戦略へつなげる
・身についた「計画力・習慣化・集中力」は大学進学後も武器になる
偏差値を5上げることは、特別な才能がなくても実現できます。戦略を立て、習慣を積み重ねることで確実に合格へと近づけます。大切なのは「今日から始める一歩」。誤答ノートや朝活など、できることから実践していきましょう。小さな積み重ねが必ず力になります。
あなたの努力は必ず報われます!
総まとめ|偏差値5アップ 行動チェックリスト
【学習戦略】
・模試・過去問で現状分析→弱点を数値化
・インプット3:アウトプット7の学習比率を守る
・週単位で逆算スケジュールを作成し、PDCAを回す
【科目別アプローチ】
・英語:単語+文法基礎→精読→長文演習
・数学:基礎問題3周→パターン化→制限時間付き演習
・国語:設問タイプ別の解法パターン化+古文単語300語暗記
・理社:一問一答反復+誤答ノートで弱点補強
【+αの工夫】
・ケアレスミス防止の仕組み化(チェックリスト・見直し時間)
・スマホ依存を断ち切り、集中環境を整える
・朝活で暗記・苦手克服タイムを確保
・「自分専用の誤答ノート」で弱点を見える化
【直前期の戦略】
・残り1ヶ月は「得点源科目」に絞る
・凡ミス撲滅作戦で確実に点数を積み重ねる
・合格者の実践法(朝型生活・誤答ノート総仕上げ・時間制限付き過去問演習)を取り入れる
【メンタル戦略】
・毎日「小さな成功体験」を積み重ねる
・ライバルではなく「昨日の自分」と比較する
・集中が切れたら運動・休憩・場所替えでリセット
【未来視点】
・偏差値+5は通過点。最終目標は「合格点の獲得」
・受験で培った「計画力・習慣化・集中力」は大学進学後の武器になる