「模試の判定はCのまま…。あと1ヶ月しかないのに、このままじゃ第一志望は届かないかもしれない。」
そんな不安を抱えているあなたへ。
実は、残り1ヶ月でも偏差値を5上げて逆転合格を狙う方法があります。
必要なのは「膨大な勉強時間」ではなく、戦略的に得点を積み上げる正しいやり方です。
この記事では、実際にC判定からB判定へと伸びた受験生の事例や、すぐ真似できる学習スケジュール、
偏差値を効率的に上げる具体的な方法を徹底解説します。
【はじめに】「1ヶ月で偏差値5上げる」は可能なのか?
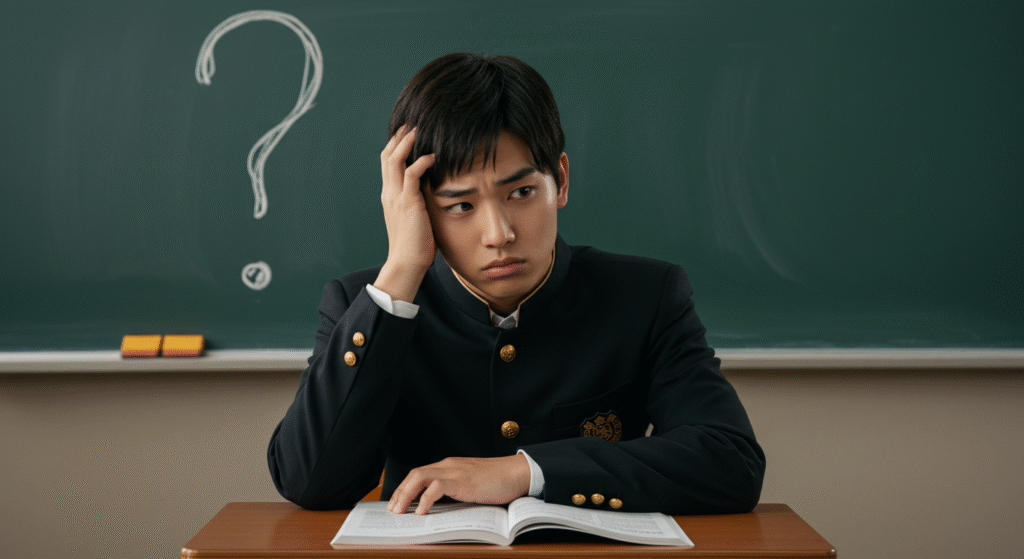
「模試の結果が思ったより悪かった」「第一志望に届くにはあと少し」──
そんな焦りの中で、「1ヶ月で偏差値5上げる」と検索したあなたは、きっと“まだ諦めたくない”気持ちを持っているはずです。
結論から言えば、1ヶ月で偏差値を5上げることは可能です。
ただし、それは「奇跡」ではなく、“戦略と分析で掴み取る成果”です。
偏差値は「相対評価」であり、単に得点を上げるだけではなく、他の受験生より効率的に得点を伸ばすことが求められます。つまり、「時間を増やす」よりも「正しい方向に努力する」ことがカギです。
特に1ヶ月という短期間では、闇雲に勉強するのではなく、“伸びる部分を見極めて一点集中する”ことが成果を左右します。
この章では、「なぜ多くの受験生がこのキーワードを検索するのか」、そして「偏差値5アップとは何を意味するのか」を具体的に解説します。
焦りや不安を感じている人ほど、ここで“正しい理解”を持つことが結果への最短ルートになります。
受験生がこのキーワードで検索する背景(焦り・不安・逆転合格への希望)
「1ヶ月で偏差値5上げる」と検索する受験生の多くは、強い焦りと不安を感じています。
模試でD・E判定を取ってしまったり、志望校まであと少しの差が埋まらなかったり──そんなとき、人は「短期間で巻き返す方法」を探し始めます。
このキーワードに込められているのは、単なる情報収集ではなく、「逆転できる希望を見つけたい」という心理です。
「本番まで1ヶ月しかないけれど、まだ上げられる?」「勉強法を変えたら可能性はある?」という切実な思いが、検索行動につながっています。
たとえば、夏以降の模試で思うように結果が出ず、「もう無理かもしれない」と思っている人も多いでしょう。
しかし、ここで諦めてしまうのはもったいないのです。なぜなら、偏差値は“努力の量”ではなく“努力の方向性”で変わる指標だからです。
多くの成功例に共通しているのは、次の3つの要素です。
- 自分の弱点を冷静に分析し、学習範囲を絞った
- 復習を習慣化し、「ミスを繰り返さない仕組み」を作った
- 得点効率の高い単元に集中し、得意分野を活かした
たとえば、教育データ分析を行う「スタディプラス」のレポートによると、
短期間で偏差値を上げた受験生の約7割が「勉強時間よりも“復習のタイミング”を重視していた」と答えています。
(参考:Studyplus 受験データレポート)
つまり、焦って量をこなすのではなく、「復習・弱点克服・集中」の3点を徹底した人が短期間で結果を出しているのです。
「1ヶ月で偏差値5上げる」という目標は、正しい戦略さえ立てれば、決して夢物語ではありません。
偏差値の仕組みと「5アップ」の意味(相対評価の理解)
ここで知っておきたいのが、「偏差値5アップ」がどれほどの意味を持つのか、ということです。
偏差値は“相対評価”であり、あなたの得点が全体の中でどの位置にあるかを示しています。
したがって、偏差値を5上げるというのは、「自分の得点を上げる+他の受験生よりも速く伸びる」という二重の条件を満たす必要があるのです。
偏差値5アップが持つ実際のインパクト
「偏差値を5上げる」と聞くと小さな変化のように思えますが、実際には全体順位が大きく動くレベルの成果です。
下記の表を見れば、そのインパクトがよく分かります。
| 現在の偏差値 | 目標偏差値 | 上昇率の目安 | 到達レベル |
| 45 → 50 | 約15%上昇 | 平均レベルへ到達 | 下位層から脱出し、全体の中位へ |
| 50 → 55 | 約30%上昇 | 上位20%レベル | 合格圏に入る可能性が見え始める |
| 55 → 60 | 約10%上昇 | 上位10%レベル | 難関大・上位校の競争層に突入 |
つまり、偏差値5アップは数百人単位でライバルを抜くほどの変化を意味します。
「1ヶ月で偏差値5上げる」というのは、志望校への距離を一気に縮めるだけでなく、自信を取り戻すきっかけにもなるのです。
偏差値は“絶対評価”ではなく“相対評価”
偏差値は「平均点」や「他の受験生の出来」に左右されるため、同じ得点でも試験ごとに結果が変わります。
たとえば、平均点が高い模試では偏差値が下がり、平均点が低い模試では偏差値が上がることもあります。
したがって、偏差値=実力のすべてではないことを理解することが大切です。
効率的に偏差値5上げるための考え方
1ヶ月で偏差値を上げるためには、努力の「量」より「質」を重視しましょう。
次の3つのポイントを意識することで、限られた時間でも偏差値は大きく動きます。
① 出題頻度の高い範囲に集中する
短期間では、出題頻度が高い単元を優先するのが最も効率的です。
英語なら文法と長文、数学なら関数・確率、国語なら現代文の要約力など、配点の大きい範囲に集中しましょう。
② 苦手科目を“平均点レベル”まで底上げ
偏差値は総合力で決まるため、1科目の苦手が全体を引き下げることがあります。
得意科目をさらに伸ばすよりも、苦手を平均まで上げる方が偏差値全体を効率的に引き上げることができます。
③ 復習を“翌日”に行う習慣をつける
日本心理学会の研究によると、学習内容を24時間以内に復習することで記憶定着率が約2倍になることが明らかになっています。
(出典:日本心理学会|学習と記憶の研究)
1ヶ月という短期間では、この“翌日復習”が偏差値アップのカギを握ります。
偏差値5アップは、奇跡ではなく戦略の結果です。
焦りや不安は、行動するためのエネルギーに変えられます。
「今からでも間に合う」──それを証明するのは、これからのあなたの1ヶ月です。
【結論】1ヶ月で偏差値5上げるための3つの条件
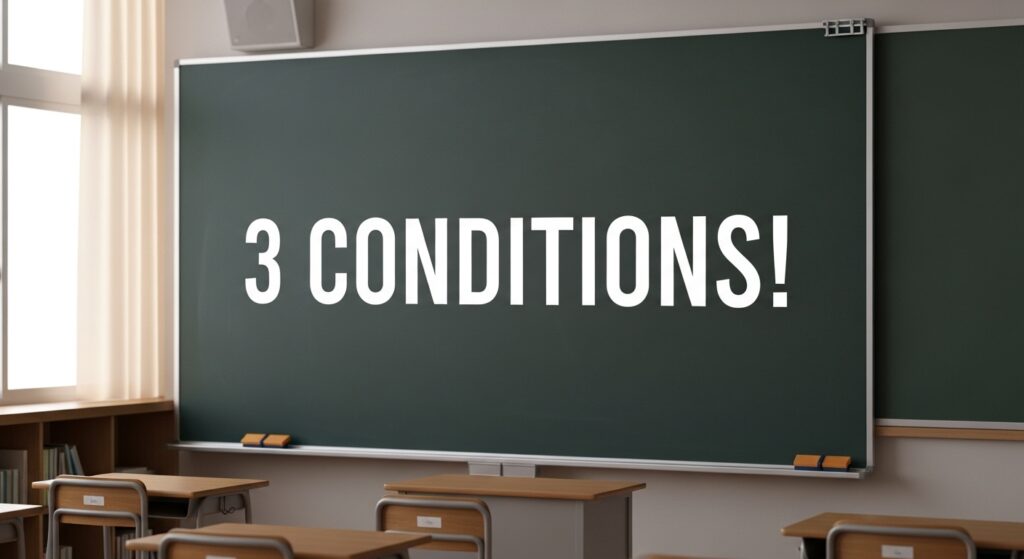
「1ヶ月で偏差値5上げるなんて無理では?」と思うかもしれません。
しかし、実際には条件を正しく整えれば十分に可能です。
偏差値は“才能”ではなく、“正しい戦略と行動”で動かせる指標です。
ここでは、1ヶ月という限られた期間で成果を出すために欠かせない3つの条件を解説します。
- 必要な学習時間を確保すること(150〜250時間)
- 学習戦略を誤らないこと(頻出分野に集中)
- 模試・過去問で進捗を検証し続けること
この3条件を正しく実践すれば、「偏差値5アップ」は現実的に達成できます。
必要な学習時間の目安(150〜250時間)
1ヶ月で偏差値を上げるには、学習時間の「量」と「質」の両方が欠かせません。
目安としては、1日あたり5〜8時間、合計150〜250時間の勉強時間が必要です。
ただし、「時間を増やす」だけでは意味がなく、目的を明確にした時間配分が求められます。
① 学習時間を「目的別」に分ける
短期間で結果を出すには、勉強時間を下の3つに分けて管理すると効果的です。
| 学習の目的 | 時間配分 | 内容の例 |
|---|---|---|
| インプット(理解) | 約40% | 授業・参考書・映像講義で基礎確認 |
| アウトプット(演習) | 約40% | 過去問・問題集を使った実戦演習 |
| 復習・分析 | 約20% | ミス直し・弱点克服・進捗管理 |
このようにバランスを取ることで、記憶と理解の両面から実力を定着させることができます。
② “やりっぱなし勉強”をなくす
問題を解いて満足してしまう勉強法では、偏差値は上がりません。
間違いを放置せず、翌日に復習する習慣をつけましょう。
日本心理学会の研究によると、学習内容を24時間以内に復習することで記憶定着率が約2倍になることが報告されています。
(出典:日本心理学会|学習と記憶の研究)
1ヶ月で結果を出すには、「復習を前提にした勉強設計」を意識することが大切です。
学習戦略を誤らないこと(頻出分野に集中)
1ヶ月という短期間では、すべての範囲を完璧に仕上げるのは現実的ではありません。
だからこそ、「出題頻度の高い範囲」に絞ることが鍵になります。
① 頻出テーマを狙う
主要科目ごとに、過去問分析から見えている“得点源になりやすい分野”を把握しましょう。
- 英語:文法(時制・関係詞・仮定法)+長文読解
- 数学:二次関数・確率・ベクトル
- 国語:現代文の論理展開・古文単語・漢文句法
このように、限られた範囲で得点を最大化することが、短期間での偏差値アップには欠かせません。
② 苦手克服より“得点効率”を重視する
苦手を克服しようとすると時間が足りなくなります。
1ヶ月で偏差値を上げる場合は、「あと少しで点が取れそうな単元」を確実に伸ばすことを優先しましょう。
苦手分野の克服はその後でも構いません。まずは「得点を稼ぐための戦略」を取ることです。
③ 集中力を守る環境を整える
どれだけ計画が完璧でも、集中できなければ意味がありません。
SNS通知を切る、学習アプリ以外を削除する、図書館や自習室を活用するなど、“1ヶ月だけ集中できる環境”を作りましょう。
模試・過去問で進捗を検証し続けること
学習計画を立てても、実際に偏差値が上がっているかを検証しなければ意味がありません。
「やりっぱなし」ではなく、「結果を分析して次に活かす」ことが必要です。
① 週1回の“ミニ模試”で実力を測る
週ごとに過去問や模試を使い、自分の理解度をチェックしましょう。
1ヶ月の中で“改善サイクル”を回すことが、偏差値アップにつながります。
また、模試の結果は「合格可能性」ではなく「弱点発見ツール」として使うのがポイントです。
② 成績を“見える化”してモチベーションを維持
勉強アプリやノートに得点・時間・進捗を記録し、グラフ化して確認しましょう。
視覚的に伸びを感じることで、勉強への集中力が高まります。
「数字で成長を確認する」ことは、継続のモチベーション維持に直結します。
③ 模試の復習が最重要
模試や過去問は“受けっぱなし”にせず、誤答分析の時間を必ず取りましょう。
次のように原因を分類すると、改善の方向が明確になります。
| 原因分類 | 具体例 | 改善策 |
|---|---|---|
| 知識不足 | 単語・公式を覚えていない | 暗記カード・音読復習 |
| ケアレスミス | 計算ミス・読み間違い | 手順を声に出して確認 |
| 思考不足 | 解法のパターンが浮かばない | 類題を3問連続で練習 |
模試後の2〜3日を「分析・対策期間」として確保するだけで、次の模試での得点が確実に上がります。
まず確認すべき!あなたの現状分析ステップ

「1ヶ月で偏差値5上げる」は、根性論ではなく“設計力”の勝負です。最初の数日を現状分析に使えるかどうかで、残りの約4週間の伸びが決まります。
ここでは、今日からそのまま実行できる3つの診断ステップを示します。いずれも配点効率・データ読解・学習時間の現実値という“数字の物差し”で判断するのがポイントです。焦りをそのまま勉強量に変える前に、まずは勝ち筋を見つけるための棚卸しを終わらせましょう。
科目ごとの穴を“配点効率”で診断する
「弱点=やるべき」ではなく、“短期間で点に直結する弱点”から先に潰します。判断基準は配点効率(=1時間あたり何点上がる見込みか)です。
配点効率を見積もる3つの質問
- 出題頻度は高いか?(過去3〜5年の模試・本試で毎回のように出る内容か)
- 伸び代はあるか?(基礎が通じる単元で、理解→演習→定着が1週間内に回せるか)
- 失点理由は明確か?(ケアレスか知識欠落か手順ミスか、原因が特定できているか)
この3条件を満たす単元は、1ヶ月スパンで最優先にします。
主要科目の“短期で効く”例
- 英語:文法(時制・関係詞・仮定法)/長文の設問パターン(指示語・同意表現・論理関係)
- 数学:II・Bなら二次関数・確率・ベクトル(典型手順で配点が大きく、反復が効く)
- 国語:現代文の“設問先読み→本文マーキング→根拠抽出”の型/古文単語・助動詞/漢文の句形
- 理科・社会:用語・法則・年代など暗記→即点の範囲(頻出テーマの一問一答+典型論述)
出題頻度の把握には、模試の講評・出題範囲表・シラバスを活用しましょう(例:進路情報や模試講評の公開資料: Benesse教育情報 / 学習指導要領の骨子: 文部科学省 )。
優先度の付け方(90分で終わる棚卸し)
- 直近2回の模試成績表を机に出す
- 各科目で誤答が多いのに配点が高い単元に★印
- ★印のうち、公式や基本語彙の暗記で即改善できるものに◎
- ◎→★→その他の順で翌週の学習計画に割り付け
模試データを読み解く!得点源と失点パターンを特定
模試は偏差値発表の場ではなく、誤差を潰すためのデータ取得の場です。成績表の“見るべき数字”を固定しましょう。
見るべき4指標
- 設問別正答率:全国正答率50〜70%帯で落としている設問=最優先の取り返しゾーン
- 大問別配点比率:配点が大きいのに取り切れていない大問=費用対効果が高い
- 時間配分の崩れ:最後の大問の空欄/途中の飛ばし=戦略の問題
- 設問タイプ別ミス:英語の照応・同意、数学の処理手順、国語の根拠位置など“型”で分類
模試成績の見方の基本や統計の読み方は、研究機関の資料が参考になります: 国立教育政策研究所(学力調査・報告書) 。
誤答原因を“型”で仕分け(テンプレ)
- 知識欠落:単語・公式・年代・定義が曖昧
- 対策:暗記カード→翌日テスト→3日後テストの間隔反復(エビングハウスの理論を応用。復習の初回は24h以内: 日本心理学会)
- プロセス欠落:途中式の省略・定型手順の抜け
- 対策:音読解法(手順を声に出す)+同型3連(同一タイプを連続3問)
- 読解の根拠ズレ:本文根拠が曖昧/設問語の取り違え
- 対策:設問先読み→根拠マーキング→選択肢照合の三段型を徹底
“ミニ模試”運用(毎週)
- 日曜午前:過去問or予想問題で60〜90分一本勝負
- 午後:誤答の型分類→原因と次週タスク1つに集約
- 週内:タスクの再テスト(15分×2回)で改善確認
学習ログの可視化は実行率を高めます。勉強時間・正答率の記録運用例や実証は、学習データ可視化の事例があるサービス資料が参考になります: Studyplus Info 。
現実的な勉強可能時間を数値化する(平日/休日シミュレーション)
1ヶ月で偏差値5を狙うなら、150〜250時間(1日あたり5〜8時間)が目安です。まずは確保可能時間を“現実ベース”で算出し、そこから逆算します。
平日・休日の可処分時間を出す
- 平日:起床・通学・授業・部活・食事・風呂・就寝をタイムライン化
- 例:通学往復90分 → 英単語×30分+リスニング×30分に置換
- 休日:午前・午後・夜の3ブロック制で“集中科目”を割り当て
配分テンプレ(そのまま埋めて使える)
- 平日(合計5h)
- 通学(往復):英単語/リスニング(1h)
- 放課後:頻出テーマの演習(2h)
- 夜:誤答の翌日復習+暗記(2h)
- 休日(合計8h)
- 午前:配点高テーマの演習+過去問1セット(3h)
- 午後:過去問直し・類題3連(3h)
- 夜:暗記棚卸し・ミニ模試復習(2h)
学習の“目的別”時間割(短期用)
| 学習の目的 | 推奨比率 | 具体例 |
|---|---|---|
| インプット(理解) | 40% | 参考書・講義で基礎の穴埋め |
| アウトプット(演習) | 40% | 過去問・標準問題の反復(同型3連) |
| 復習・分析 | 20% | 誤答の型分類→翌日・3日後で追試 |
継続を壊さない“1ヶ月だけの約束”
- スマホ通知を勉強アプリ以外オフ
- 勉強開始時にポモドーロ25分×4を最低ライン
- 1日の最後に“明日の最初の1問”を付箋で決める(立ち上がり損失をゼロに)
(参考)分析でよく出るQ&Aに即答
Q. 苦手科目と得意科目、どちらを先に?
A. 総合偏差値を動かすなら“平均未満の科目を平均へ”が先。 得意は維持管理に留め、時間の8割を“平均化”に回すと伸び率が高い。
Q. 過去問はいつから?
A. 今すぐ週1でミニ模試運用。 解く→直す→同型3連までが1セット。年度をまたいで“設問タイプ”で比較する。
Q. 暗記はどのタイミングが最適?
A. 就寝前10分→翌朝10分→通学30分。 初回復習は24h以内が最重要です(エビングハウス忘却曲線:概念の解説は 日本心理学会 )。
1ヶ月短期集中で偏差値を上げる学習法
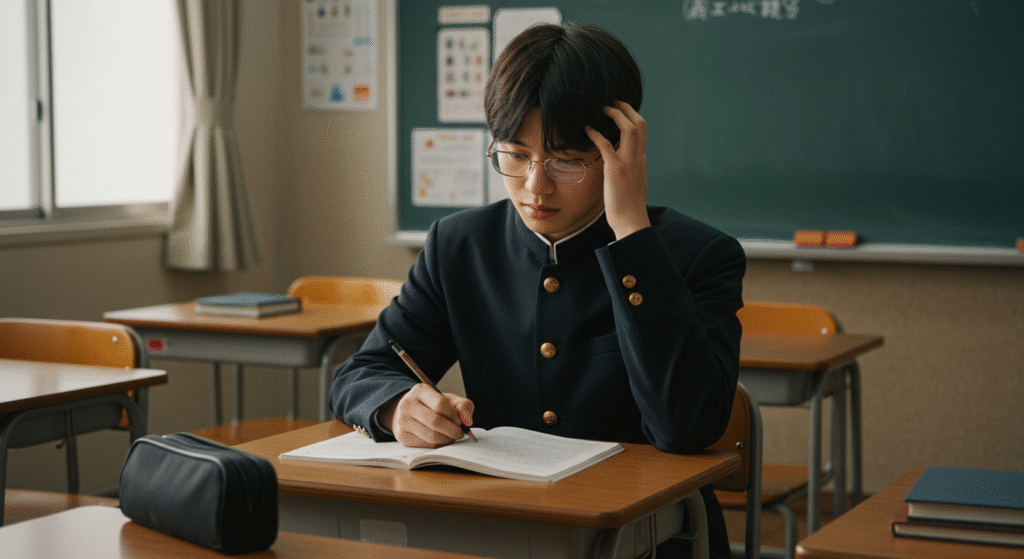
「模試の結果が悪くて焦っている」「あと1ヶ月でなんとか結果を出したい」。そんな受験生にとって、短期間で偏差値を上げるのはまさに時間との戦いです。しかし、学習法を根本から見直せば、1ヶ月でも偏差値を5上げることは十分可能です。
ここでは、限られた期間で最大の成果を出すための具体的な方法を紹介します。
共通の学習原則(インプット3:演習6:復習1の黄金比)
最短で偏差値を上げるには、学習配分がカギです。最も効果的なのが「インプット3:演習6:復習1」という比率です。
- インプット(3):教科書・参考書などで新しい知識を吸収する。
- 演習(6):問題を解いて知識を定着させる。
- 復習(1):間違いの原因を分析し、弱点を補強する。
短期間で結果を出すためには、暗記よりも「使える知識」に変えることが大切です。演習を中心に据え、ミスの傾向を把握して復習に活かすことで効率的に得点力が上がります。
実践ポイント
- 1日の学習時間を均等に分けず、「演習」に最も多く時間を割く。
- 復習は夜にまとめて行うことで記憶の定着を促進。
- 「理解した気になる時間」を減らし、「手を動かす時間」を増やす。
短期で確実に形にしたいなら「個別最適化」の活用を
「1ヶ月で偏差値を上げたい。でも自分に合う具体策が分からない」方は、オンラインのメガスタで “合格から逆算したカリキュラム”を作ってもらうのがおすすめです。
- 総合型選抜・推薦入試に強いノウハウ(志望理由書・面接・小論文まで一貫対応)
- 1対1の個別指導/少人数指導で「演習6:復習1」を個別設計
- 大学の採点基準を踏まえた“点になる”指導で短期の伸びに直結
- オンライン完結で通塾時間ゼロ、学習時間を最大化/料金も手頃
まずは無料相談で現状分析→1ヶ月プランの叩き台を作ってもらうだけでも価値があります。
【英語】長文演習+語彙1000語の周回で得点効率UP
英語は語彙力と読解力の掛け算です。この2つを同時に伸ばすことで、1ヶ月でも偏差値を5上げることが可能です。
【ステップ1】語彙1000語を繰り返し覚える
1日40語×25日で1000語を目標に設定します。完璧を目指すよりも、何度も繰り返して「見た瞬間に意味が出るレベル」を目指しましょう。単語帳は「ターゲット1900」や「システム英単語」など定番の一冊を使えば十分です。
【ステップ2】長文読解は毎日1題を解く
1日1題の長文演習をルーティン化することで、読解スピードと正答率が同時に向上します。制限時間を15分と決めて解き、解説を10分で分析するサイクルを習慣化するのが理想です。
共通テスト形式の長文問題は、河合塾やZ会の教材を活用すると効果的です。
【数学】典型解法パターンの徹底暗記+タイムアタック
数学で短期間に伸びる人の共通点は、「考える前に手が動く」状態を作っていることです。そのために必要なのが、典型問題のパターン化と時間管理の訓練です。
【ステップ1】よく出る30題を完全暗記
基礎~標準レベルの問題集から頻出の解法パターンを30題ピックアップします。公式を覚えるだけでなく、式の流れや途中の考え方を説明できるようにしましょう。教材は青チャートや「基礎問題精講」などが最適です。
【ステップ2】タイムアタックで解法スピードを鍛える
1題10分を目安に時間を測りながら演習します。解き終えたら、必ず間違いの原因を分析。解法を覚えるだけでなく、時間内に正確に処理できるスキルを養うことが重要です。
【国語】現代文の設問パターン攻略/古文単語300+文法必修
国語は「出題者の意図」を掴めば確実に伸びます。現代文と古文それぞれで効率的な伸ばし方を紹介します。
【現代文】設問形式を攻略する
共通テストでは「指示語」「理由説明」「主張要約」など、設問パターンはほぼ固定されています。毎日2題程度を解き、解説を通して“どうしてこの選択肢が正解なのか”を分析することで読解の軸が安定します。
【古文】単語300+文法の徹底暗記
古文は知識科目です。まずは頻出300語を音読して覚え、助動詞の意味と接続を文法書で確認しましょう。おすすめは旺文社の古文単語315と「マドンナ古文」。これを完璧にすれば古文の点数は劇的に安定します。
【理社】通史1周→テーマ別まとめノート→一問一答逆引き演習
理科・社会は「量の多さ」との戦いです。1ヶ月で結果を出すためには、最初に全体像を掴み、その後に知識を整理しながら繰り返すことがポイントです。
【ステップ1】通史や全範囲を3〜5日で1周
細部にこだわるよりもまず全体の流れを掴みます。動画授業を使うと効率的で、スタディサプリなどを活用すれば短期間で知識が整理されます。
【ステップ2】テーマ別まとめノートで整理
「原因→結果→影響」を3行で簡潔にまとめることで、理解が深まり記憶が長持ちします。自分の言葉で書くことが重要です。
【ステップ3】一問一答を“逆引き”で演習
正解を覚えるよりも「間違った問題」を中心に回す方が効果的です。一問一答は山川出版社の教材など、基礎~共通テストレベルの問題を使うとよいでしょう。苦手な項目だけを繰り返す「逆引き学習」で、短期間でも抜群の定着が期待できます。
時間割テンプレート(すぐ真似できる学習スケジュール)

「1ヶ月で偏差値を5上げたい」と思っても、実際にどのように時間を使えば良いか迷う人は多いでしょう。限られた時間をどう配分するかで、結果は大きく変わります。
ここでは、1日ごとの理想的な時間割と、1ヶ月を4段階で進める“短期集中ロードマップ”を紹介します。
平日4時間の使い方(通学+夜学習)
学校や部活がある平日は、1日の自由時間が限られています。そこで重要なのは「スキマ時間の最大活用」と「夜の集中タイムの確保」です。
【朝】通学時間を「暗記ゾーン」にする
朝は脳がリフレッシュしている時間。英単語や古文単語など、暗記系に最適です。単語アプリ(スタディサプリやmikanなど)を活用し、通学の30分を「インプットの習慣化」に変えましょう。
【放課後〜夜】問題演習中心の2時間ブロック
放課後〜夜は、理解した内容を“使える知識”に変える時間。科目ごとの理想的な時間配分は以下の通りです。
- 英語:長文1題+語彙復習(60分)
- 数学:典型問題2〜3題を反復(60分)
- 理社:一問一答やノートまとめ(30分)
- 国語:現代文1題 or 古文文法確認(30分)
寝る前の15分は、ミスノートを確認して「記憶の再定着」を行うのがおすすめです。夜に復習することで、睡眠中に記憶が整理されやすくなります。
【ポイント】勉強時間より「習慣化の型」
4時間の中で「やる時間を固定する」ことが何より大切です。毎日同じ時間に机に向かうリズムを作ることで、集中力を高め、勉強への抵抗感を減らせます。
休日10時間の効率配分
休日は「平日の2倍」ではなく、「質を2倍」にする日です。1日10時間を最大限に活かすために、集中と休憩のリズムを明確にしましょう。
理想の時間割テンプレート(10時間版)
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 8:00〜10:00 | 英語長文+文法演習(集中ブロック) |
| 10:15〜12:15 | 数学の演習(苦手分野の克服) |
| 12:15〜13:30 | 昼休憩&軽い散歩でリフレッシュ |
| 13:30〜15:30 | 理社のまとめノート作成 |
| 15:45〜17:45 | 過去問1年分 or 模試復習 |
| 18:00〜19:00 | 食事・休憩 |
| 19:00〜21:00 | 暗記系・弱点復習(英単語/古文単語など) |
ポイントは「90分×5セット+小休憩」の構成にすること。長時間机に向かうより、集中→休憩→集中のサイクルで脳をリセットしながら取り組む方が、記憶効率が高まります。
また、午後は一番眠くなる時間帯です。ここに「作業系」(ノートまとめや整理)を置くことで、集中が切れても生産性を維持できます。
夜の“再現学習”で記憶を固定
1日の終わりには、朝にやった内容を10分で再確認。アウトプット形式で友達に説明するつもりで声に出して復習すると、記憶が定着しやすくなります。
週ごとのロードマップ(基礎→過去問→演習→最終調整)
1ヶ月で偏差値を上げるためには、「週ごとの到達目標」を明確に決めることが重要です。ここでは、1ヶ月を4週間に区切った学習ロードマップを紹介します。
【第1週】基礎の総復習
まずは“苦手の把握”と“基礎の穴埋め”からスタート。特に数学・英語は、基礎が曖昧だと後半の演習が無駄になります。過去の模試を見返し、弱点を明確にしてから教材を絞りましょう。
- 英語:単語帳1冊を3日で1周(ざっくり)
- 数学:教科書例題・青チャートレベルを再確認
- 国語:設問分析ノートを作成
【第2週】過去問で出題傾向を掴む
この週の目的は「出題者の意図を知る」こと。いきなり難問に挑まず、1日1年分の過去問を解いて解説を熟読します。特に英語・国語は「設問の型」を分析すると、得点の伸びが加速します。
【第3週】分野別の演習強化
過去問で見つけた弱点をピンポイントで補強します。数学は「苦手分野を1冊にまとめ」、英語は「長文の要約練習」でスピードを上げます。
- 数学:苦手単元ノートを作成し、類題を5題ずつ解く
- 英語:長文10本ノック(時間制限付き)
- 理社:一問一答を使って逆引き演習
【第4週】最終調整とアウトプット中心
本番直前の1週間は“まとめ期”。新しい問題には手を出さず、解いた問題の「やり直し」と「解答プロセス確認」を徹底します。
- 過去問の解き直し3回目(時間を測って実戦モード)
- 間違いノートの再チェック
- 本番時間に合わせて学習リズムを調整
1ヶ月の総仕上げは「知識の量」より「思考の速さと正確さ」。試験当日の感覚を意識して取り組むことで、短期でも確実に偏差値を5上げる実力が身につきます。
得点を伸ばす“戦略的演習”のコツ

「勉強しているのに点数が上がらない」「あと数点で合格圏に届かない」──
そんな悩みを抱える受験生の多くは、実は“演習のやり方”に問題があります。1ヶ月で偏差値を5上げるためには、ただ解くだけの勉強ではなく、得点に直結する“戦略的演習”が必要です。
ここでは、模試・過去問・ミス対策という3つの軸から、短期間で成果を出すための演習法を解説します。
模試の活用法!「ライバル全体」を意識した相対評価対策
模試を「成績表を見るためのイベント」として終わらせていませんか? 本来、模試は「全国のライバルに勝つための練習試合」です。1ヶ月で偏差値を上げるには、絶対評価ではなく相対評価の観点で分析することが重要です。
【ステップ1】平均点との差を算出する
成績表を見たら、まず「平均点との差」をチェックしましょう。偏差値はこの差で決まります。たとえば、英語で平均点が60点・自分が65点なら+5点差です。偏差値を5上げたい場合、全科目で平均+5点を積み上げることが1つの目安になります。
【ステップ2】正答率から「取りこぼしゾーン」を特定
模試の設問別データ(正答率)を見て、正答率40〜70%の中間層問題でミスした箇所をマークします。そこは「周囲の受験生が解けるのに自分は落としている」ゾーン。逆に、正答率20%以下の難問は切り捨ててOKです。効率よく得点を伸ばすためには、この中間層を確実に取る練習に集中しましょう。
模試を“受けっぱなし”で終えるのではなく、「どこでライバルに差をつけられているか」を明確にする。これが、戦略的演習の第一歩です。
過去問の3回転学習法(把握→定着→実戦)
過去問演習は最も得点アップに直結しますが、解くだけでは意味がありません。効果を最大化するための方法が、「3回転学習法」です。
【第1回転】全体把握(傾向を掴む)
初回は「結果を出す」よりも「出題傾向を掴む」ことを目的にします。制限時間を設けず、出題分野・設問形式・記述量などを丁寧に確認します。例えば英語なら、長文の語数や設問パターンをメモ。数学なら、頻出の分野(微積・確率など)を分類してリスト化しておくと効果的です。
【第2回転】定着(理解を深める)
2回目は、1回目で間違えた問題に集中。特に「わかったつもり」の問題を重点的に再演習します。解説を読むだけで終わらせず、ノートに“なぜそうなるのか”を自分の言葉で書き出しましょう。手を動かすことで、理解が思考に変わります。
【第3回転】実戦(時間内で解き切る)
3回目は本番と同じ時間設定で実施。得点だけでなく、「解く順番」「見直し時間」を意識してシミュレーションします。制限時間内に得点を最大化する練習を重ねることで、試験本番の緊張感にも強くなります。
過去問を3回転することで、知識→理解→実戦の流れが完成します。多くの受験生は「解くだけ」で終わりますが、この“回転学習”を行えば、1ヶ月でも偏差値5アップは十分に可能です。
ケアレスミスをゼロにするチェックリスト(符号・桁・単位・設問読み)
「わかっていたのに間違えた」──偏差値を上げる上で最ももったいない失点がケアレスミスです。実は、このミスは意識的に潰すことができる“技術”です。以下のチェックリストを、毎回の演習後にルーティン化してください。
ケアレスミス防止チェックリスト
- 符号:+と−の書き間違いがないか。途中式で符号が反転する箇所を赤ペンで囲む。
- 桁:計算結果の桁ズレや0の数を再確認。特に掛け算・割り算での桁落ちは注意。
- 単位:物理・化学での「cm⇔m」「g⇔kg」などを確認。問題文の単位に合わせる。
- 設問読み:「正しいもの」「誤っているもの」の指定を読み違えないようマークする。
また、模試や過去問の復習時には、「自分のミスの傾向表」を作ってください。符号ミス、設問読み違え、計算ミス…などを分類し、週に1回見直すだけで再発率が大幅に下がります。
東進ハイスクールの学習法ページ(東進ハイスクール公式サイト)でも紹介されているように、ミスの原因を“分析して再現防止”する姿勢こそ、上位層が徹底しているポイントです。
ケアレスミスをゼロにすることは、難問を1問解くよりも効果的な得点アップ戦略。短期間で偏差値を上げたい人ほど、まず「確実に取る力」を磨きましょう。
よくある悩みと解決策(FAQ形式)
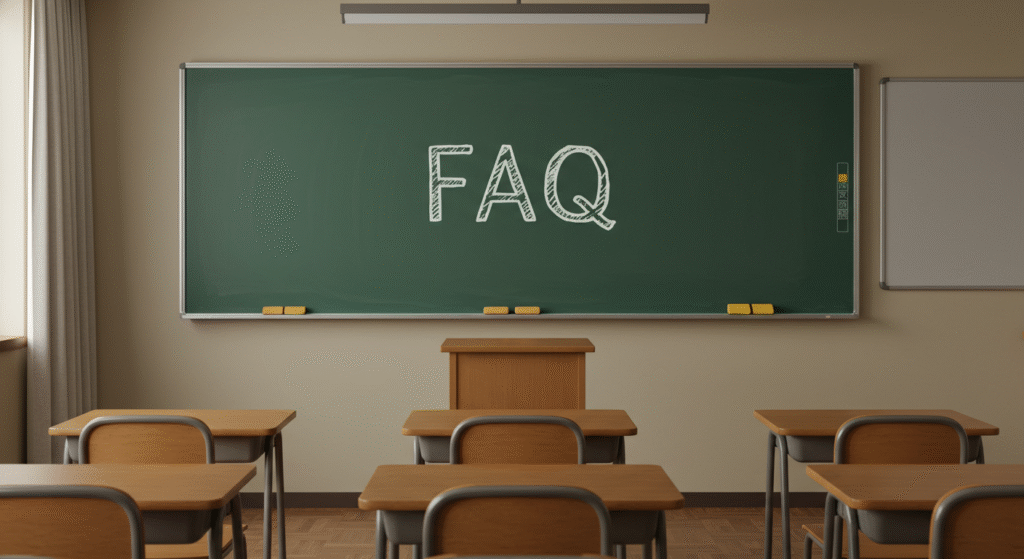
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「時間が全然足りない」「模試の判定が変わらない」──。 1ヶ月で偏差値を5上げたい受験生が抱える悩みは、ほとんどがこの3つに集約されます。
ここでは、それぞれの悩みを“原因”と“具体的な解決法”に分けて解説します。今日からすぐ実践できる内容ばかりです。
「時間が足りない」→スキマ時間の活用法(音声暗記・カード化)
学校や塾で一日が終わってしまうと、「家で勉強する時間が取れない」と感じる人は多いでしょう。 しかし、実際には1日あたり2〜3時間の“スキマ時間”が眠っています。 この時間を活用できるかどうかで、1ヶ月後の偏差値は大きく変わります。
【ステップ1】通学・移動時間を「耳の勉強時間」にする
音声での学習は、目の疲れを防ぎながら記憶を定着させる効果的な方法です。 英単語・古文単語・社会の用語集などを音声化し、通学や家事の時間に聞き流しましょう。 おすすめはスタディサプリなどの講義アプリや、スマホの録音機能を使って自分の声で単語帳を作る方法です。
【ステップ2】暗記カードで“1分単位の復習”を習慣化
待ち時間や寝る前の1分でも使えるのが、カード学習。 英単語カードやアプリ(mikanなど)を使って、「わかる/わからない」を瞬時に仕分けします。 暗記は“短く・何度も”が基本。1回の勉強時間を伸ばすより、回数を増やす方が記憶に残りやすくなります。
時間がないと感じる人ほど、「まとまった時間」ではなく「スキマ時間の総量」を意識してみましょう。 1日15分の積み重ねで、1ヶ月後には7時間以上の学習差が生まれます。
「やっても伸びない」→復習ルール1:3を徹底する
「毎日勉強しているのに結果が出ない」という悩みの多くは、復習不足が原因です。 脳科学的にも、記憶は“思い出す回数”に比例して定着します。 そこでおすすめなのが「復習ルール1:3」です。
ルール1:3とは?
学習した翌日・3日後・1週間後の3タイミングで復習するという方法です。 忘却曲線の理論によると、人は24時間で学んだ内容の約7割を忘れるといわれています。 この“忘れる前のタイミング”で復習を入れることで、記憶の保持率を高めることができます。
実践例(英単語の復習スケジュール)
- 1日目:新しい単語100語を学習
- 2日目:昨日の100語を復習+新出50語
- 4日目:初日の100語を再チェック
- 7日目:再テスト形式で定着確認
このサイクルを守るだけで、“覚えたつもり”から“確実に定着した知識”へ変わります。 復習を「気が向いた時にやる」ではなく、「予定に組み込む」ことが大切です。 Googleカレンダーや学習アプリのリマインダー機能を活用すれば、自動化もできます。
また、復習時間を夜に設定すると、睡眠中に記憶が整理されやすくなります。 これは国立遺伝学研究所の研究でも裏付けられています。
「判定が上がらない」→得点KPIで先に伸びを可視化する
模試の判定はすぐには変わりません。 しかし、「偏差値」という結果が出る前に、得点の“伸び”を見える化する方法があります。 それが得点KPI(Key Performance Indicator:主要指標)を設定することです。
得点KPIとは?
偏差値は他の受験生との相対評価ですが、KPIは「自分の成長を測る絶対指標」です。 たとえば次のような形で設定します。
- 英語:長文1題あたりの正答率を60%→80%に
- 数学:1問あたりの平均解答時間を8分→6分に
- 国語:設問読み間違いゼロを3日連続で達成
このように「行動ベース」で指標を立てると、1週間単位で小さな成果が見えるようになります。 それがモチベーションの維持につながり、結果的に偏差値上昇に直結します。
見える化のためのツール
学習管理アプリ(Studyplusなど)やスプレッドシートで日ごとの得点推移を可視化しましょう。 「今日は5点伸びた」「解くスピードが上がった」といった小さな変化を見逃さないことが、継続の原動力になります。
偏差値は「最後に上がる数字」です。 それまではKPIで“自分の伸び”を確認しながら、焦らず積み重ねていくことが成功の近道です。
1ヶ月で偏差値を上げるには、「時間」「復習」「指標」の3つを正しく設計すること。 この3本柱を回し続けることが、短期集中で結果を出す唯一の方法です。
【実例紹介】1ヶ月で偏差値5アップを達成したケース

「本当に1ヶ月で偏差値って上がるの?」──多くの受験生が最初に抱く疑問です。 結論から言えば、上がります。実際に、模試で偏差値を5以上アップさせた生徒たちは「正しい戦略」と「毎日の習慣化」を徹底していました。
ここでは、実際の成功事例をもとに、どんな工夫で成績を伸ばしたのかを紹介します。
短期間で確実に力を伸ばしたい場合は、
実践例の多いオンライン個別指導も効果的です。
勉強時間の確保と習慣化の工夫
ある高校3年生のAさんは、6月の模試で英語偏差値48からスタート。 志望校の判定はD判定でした。そこから「1ヶ月で偏差値5アップ」を目標に掲げ、次の模試で偏差値53を達成しました。
1日4時間を“固定スケジュール化”
それまで「時間があれば勉強する」という曖昧なスタイルだったAさん。 そこで1ヶ月間、「毎日4時間を同じ時間帯で勉強する」と決めました。 平日は通学・学校・家庭学習を組み合わせて、以下のようなリズムを確立。
- 朝7:00〜7:30:通学中に英単語音声を聞く
- 放課後18:00〜19:00:学校自習室で英語長文1題
- 20:00〜22:00:家庭で数学・古文の演習+復習
「毎日同じ時間にやる」と決めたことで、勉強が“特別なこと”ではなく“生活の一部”になりました。 最初の1週間はつらくても、2週目以降は“やらない方が落ち着かない”感覚になるほど、習慣化が進みました。
「記録」でモチベーションを維持
Aさんが特に効果を感じたのは、「学習記録アプリ(Studyplus)」の活用でした。 「今日やった時間」をグラフ化することで、積み上げの実感が得られ、やる気の維持につながったそうです。 記録が増えると「昨日より頑張りたい」という自然な競争意識が生まれ、結果的に学習時間が安定していきました。
偏差値アップの第一歩は、特別な才能ではなく、「毎日やる仕組み」を作ること。 Aさんのように「固定時間+記録」で学習リズムを固めることで、最初の壁を超えられる人は多いです。
得点源科目を伸ばして合格判定C→Bへ
次に紹介するのは、文系志望の高校3年生Bさん。 7月模試で全体偏差値52、志望校はC判定。そこから1ヶ月後、得意科目の国語と英語を軸に偏差値を57まで上げ、判定もBに上がりました。
得点源を「2科目」に絞って集中
多くの受験生が全科目を同じように勉強しがちですが、Bさんは「得点を伸ばしやすい科目」に集中。 国語と英語の2科目に学習時間の7割を注ぎ込み、他の科目は“維持”を目的としました。 短期間で偏差値を上げるためには、「戦略的な優先順位」が欠かせません。
特に国語では、共通テスト形式の現代文を毎日1題解き、「設問のパターン」を徹底分析。 英語では、長文演習+英単語1000語の周回を1ヶ月続けました。
- 国語:共通テスト形式の問題を1日1題×25日(精読+解説分析)
- 英語:長文15分演習+10分復習を毎晩継続
1日ごとの小さな達成を積み重ねることで、解答スピードが向上。 「設問形式に慣れる」ことが得点力アップのカギだと実感したそうです。
【結果】模試の偏差値+5、C→B判定へ
1ヶ月後の模試では、国語が+8点、英語が+12点。合計偏差値は52→57に上昇。 志望校判定もC→Bに改善し、「あと一歩でA判定」というところまで到達しました。 この結果を支えたのは、“得点源科目を明確に決めた戦略”と、“日々の習慣の継続”です。
「短期間で成績を上げたいなら、全教科を完璧にしようとしないこと」──これはBさんが実感した最大の学びです。 勝負の1ヶ月では、「捨てる勇気」と「伸ばす集中」が合格への近道となります。
1ヶ月で偏差値5アップを達成した人たちの共通点は、次の3つです。
- ① 時間を決めて勉強を“習慣化”した
- ② 得点源を明確にして集中した
- ③ 成果を“見える化”してモチベーションを維持した
つまり、「計画・習慣・可視化」を組み合わせることこそが、最短で成果を出す黄金パターン。 努力を“戦略化”すれば、1ヶ月でも偏差値を上げることは十分に可能です。
【まとめ】1ヶ月で偏差値5上げるために押さえるべきポイント
最後に、本記事で解説してきた内容を分かりやすく整理します。残り1ヶ月という短い期間でも「選択と集中」を徹底すれば、偏差値5アップは十分に可能です。
重要ポイント(箇条書き)
- 偏差値5アップは可能
→ やみくもな努力ではなく、戦略的な学習で現実的に狙える。 - 現状分析がスタートライン
→ 科目ごとの穴を「配点効率」で診断
→ 模試データから「得点源」と「失点パターン」を特定
→ 平日・休日で「現実的に使える時間」を数値化 - 学習法の黄金比を意識
→ 「インプット3:演習6:復習1」で学習を回す
→ 英語:長文+語彙1000語を周回
→ 数学:典型解法の暗記+タイムアタック
→ 国語:設問パターン攻略+古文単語・文法300
→ 理社:通史1周→テーマ別まとめ→一問一答逆引き - 時間割テンプレを活用
→ 平日:通学+夜学習で4〜5時間
→ 休日:集中10時間を「過去問+演習中心」に配分
→ 1ヶ月のロードマップ(基礎→過去問→演習→最終調整)を回す - 戦略的演習で得点を伸ばす
→ 模試は「ライバル全体の平均」を意識して分析
→ 過去問は「把握→定着→実戦」の3回転学習
→ ケアレスミスは「符号・桁・単位・設問読み」のチェックリストでゼロへ - よくある悩みの処方箋
→ 「時間が足りない」→スキマ時間を暗記専用に活用
→ 「やっても伸びない」→復習ルール1:3を徹底
→ 「判定が上がらない」→得点の伸びを“成長のものさし”として確認 - 実例紹介で学ぶポイント
→ 勉強時間を習慣化(スキマ活用・スマホ封印・午前集中)
→ 得点源科目を優先してC判定→B判定にアップ
→ 「全科目ではなく、得点効率の高い科目への投資」が成功の鍵 - 最後の1ヶ月の心構え
→ 偏差値UPは「努力量」ではなく「戦略×時間×検証」で決まる
→ 判定に振り回されず、得点の積み上げを確認する
→ 残り1ヶ月を「合格可能性を最大化する時間」として活用する
つまり、1ヶ月で偏差値5を上げる最短ルート
